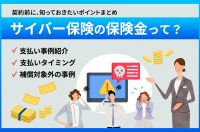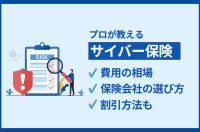近年、企業の規模を問わずサイバー攻撃の脅威は増大しており、特にセキュリティ対策が手薄になりがちな中小企業が標的とされるケースが増えています。万が一の事態に備え、事業継続を守るための一つの有効な手段として「サイバー保険」への関心が高まっています。 この記事では、中小企業がサイバー保険を検討する上で知っておくべき基本的な知識から、具体的な選び方のポイント、そして導入事例までを分かりやすく解説します。
中小企業を狙うサイバー攻撃の現状とリスク
サイバー攻撃は一部の大企業に限った話ではなく、今や企業規模を問わず発生しています。中でも中小企業は、十分な対策が取りづらいという特性から、攻撃者にとって「狙いやすい標的」として位置づけられています。
本章では、中小企業を取り巻く攻撃の実態と、そこから生じるリスクについて整理します。
近年増加する中小企業へのサイバー攻撃
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が発表した「情報セキュリティ10大脅威 2025」では、ランサムウェアによる被害や標的型攻撃による情報窃取が、企業の被害事例として上位を占めました。かつては大企業が主な標的とされていましたが、最近ではセキュリティ体制が脆弱な中小企業への攻撃が増加傾向にあります。
特に近年では、サプライチェーン攻撃という手法が注目されています。これは、大企業の取引先である中小企業のネットワークに侵入し、そこを踏み台として本来の標的にアクセスするというものです。警察庁が公表した「令和5年版サイバー空間脅威情勢」によると、こうしたサプライチェーンを起点とする攻撃は、前年比で約1.4倍に増加しています。中小企業はこのリスクの中核に位置しています。
🔗【関連コラム】
サイバー攻撃、企業の3社に1社が被害経験【2025年 帝国データバンク調査】― 中小企業も拡大傾向
中小企業が直面する具体的な被害
サイバー攻撃によって中小企業が被る被害は、単なる金銭的損失にとどまりません。事業運営の根幹に関わる影響や、顧客・取引先との信頼関係にまで波及するケースもあります。ここでは、主な被害の種類とその内容を整理します。
主な被害の内容
- 直接的な金銭流出:ランサムウェアの身代金要求、不正送金、復旧費用など
- 事業停止による損失:システムダウンによる業務停止、生産ラインの停止、顧客対応の遅延など
- 法的責任・賠償:個人情報漏えいに伴う損害賠償、訴訟費用、当局対応費用、法律相談費用
- 信用失墜:取引停止、顧客離脱、ブランドイメージの低下、風評被害など
- 復旧・対応コスト:原因調査、コンサルティング費用、再発防止策、広報対応、従業員の残業代など
🔗【関連コラム】
サイバー攻撃の企業への被害額は?億単位もありえる被害額|2024年最新版を公開
なぜ中小企業が攻撃対象になりやすいのか
中小企業がサイバー攻撃の標的となりやすい背景には、いくつかの理由が考えられます。理由1:セキュリティ投資や専門人材が不足している
中小企業では、限られた予算や人材の中で、セキュリティ対策が後回しになりがちです。IT部門を持たない企業も多く、対策が不十分なまま日常業務を行っているケースが少なくありません。 その結果、ウイルス対策ソフトやファイアウォールなどの防御策が最新の脅威に対応できておらず、攻撃を防ぎきれない状態に陥るリスクが高まります。
理由2:「自社は狙われない」という油断がある
「うちは重要な情報を扱っていない」「規模が小さいから関係ない」といった思い込みが、社内教育や初期対応体制の整備を遅らせる要因になります。実際には、社内ネットワークやクラウド、業務システムがインターネットに接続されている限り、あらゆる企業が攻撃のリスクにさらされています。
理由3:サプライチェーン攻撃の踏み台にされやすい
中小企業は、大企業との取引や連携の中でサプライチェーンの一部を担っており、セキュリティの弱点となることがあります。サプライチェーン攻撃とは、取引先や委託先など、セキュリティ対策が比較的手薄な企業を経由して、本来の標的である大企業のネットワークに侵入する手法です。
攻撃者は、セキュリティ層の薄い中小企業を起点にして、大企業のネットワークへアクセスするルートを確保しようとします。
サプライチェーンについての詳細はこちら
▼サプライチェーン攻撃とは?中小企業が狙われる理由・実例・対策まで徹底解説
攻撃者は、最小の労力で最大の成果を得ることを目的としています。
そのため、防御が甘く、波及効果の高い中小企業は効率的な標的と見なされやすいのです。自社は関係ないという思い込みを捨て、現実に即した備えを進める必要があります。
こうしたサイバー攻撃の脅威と、それに伴う経済的・社会的な損害リスクを踏まえ、中小企業においてもファイアウォールやウイルス対策ソフトの導入、社員へのセキュリティ教育など、日頃からの技術的・組織的な「セキュリティ対策」が急務です。
しかし、それでもすべての攻撃を完全に防ぎきるのは難しく、万が一に備えた「経営リスク対策」も不可欠となってきました。
そこで近年、 万が一の事態に備え、セキュリティ対策とあわせて事業継続を守る手段として「サイバー保険」への関心が高まっています。
万が一に備える経営リスク対策「サイバー保険」
どれだけセキュリティ対策を講じても、サイバー攻撃を完全に防ぎきることは困難です。そのため、被害が発生してしまった場合に備え、損失の最小化と早期復旧を支援する手段として「サイバー保険」が注目されています。
ここでは、サイバー保険の基本的な仕組みや補償内容、他の保険との違いについて詳しく解説します。
サイバー保険の定義と目的
サイバー攻撃や情報漏洩など、サイバー事故によって生じる様々な損害を補償する保険です。具体的には、損害賠償責任、事故対応費用、利益損失などを補償します。
顧客や取引先からの第三者への損害賠償請求のほか、事故調査費用、復旧費用も補償の対象になります。
サイバー攻撃の手口は年々高度化・巧妙化しており、いかに対策を講じても100%の防御は難しいのが現実です。
サイバー保険は、万が一被害を受けた際に企業の損失を最小限に抑え、事業の早期復旧と継続を支援することを目的としています。
🔗【関連コラム】 サイバー保険の必要性とは?必要な理由と個人情報漏洩保険との違いをプロが徹底解説
サイバー保険でカバーされる主な損害
サイバー保険の補償内容は、保険会社の保険商品やプランによって異なりますが、一般的に以下のような損害が対象となります。| 補償カテゴリ | 具体的な補償内容 |
|---|---|
| ① 第三者への賠償責任 |
サイバー攻撃や情報漏えいにより取引先・顧客に損害を与えた際の賠償責任を補償。 ・損害賠償金 ・訴訟対応費用(弁護士費用など) ・従業員の犯罪・背任による損害(※) など 【※補足】 たとえば「従業員が、業務上知りえた取引先企業の従業員情報を第三者に売り渡したことで個人情報漏えいが発生し、会社が損害賠償請求を受けた」といったケースも補償対象となります。 |
| ② 事故対応費用 |
サイバー事故発生後に必要な一連の対応にかかる費用を幅広く補償。 ・原因調査費用、データ復旧費用 ・被害者への見舞費用、モニタリング費用 ・記者会見・コールセンター設置などの信頼回復費用 ・弁護士・専門家への相談費用、公的報告対応費用 |
| ③ 自社の損害 |
サイバー攻撃による業務中断に伴う自社の経済的損失を補償。 ・喪失利益の補填 ・収益減少を防ぐための外注・代替措置費用 ・営業継続のための臨時費用 など |
中小企業がこうした被害を単独で負担することは困難であり、サイバー保険はその経済的リスクを軽減する有効な手段となります。
サイバー保険には種類がある
実は、サイバー保険にはいくつかの種類があります。
一般企業向けプラン、情報漏えいに特化したプラン、IT業務向けプランなどがあり、補償の範囲や重視されるリスクが異なります。
自社の業種や事業内容に応じて、適したタイプを選ぶことが重要です。
● サイバー保険(一般企業向け)
一般の企業向けのサイバー保険です。
サイバー攻撃に遭ってしまったり、社内のミスで起きたサイバー事故の際に補償されます。
● 情報漏えい保険
主にサイバー事故のうち、情報漏洩が起因した事故による損害だけをカバーします。
● IT業務向けサイバー保険
システム開発会社やクラウド事業者など、
IT業種特有のリスクや、業務請負に伴う業務過誤に対応しています。
IT業務に携わる場合は、IT業務専用の損害賠償保険の導入でリスクに備える必要があるため、下記ページをご参照ください。
IT業務用サイバー保険
たとえば情報漏洩保険の補償は、情報漏洩が起因した事故に限定した補償のため、「不正アクセスがありECサイトが改ざんされた」「ランサムウェア攻撃により情報漏洩はなかったものの、システムやデータが破損した」「システムの乗っ取りにより、工場に火災が発生し近隣住人を巻き込んだ」のような事故では、情報漏洩がされていないため補償がされません。
このことから自社の事業内容に合ったタイプを選ぶことが重要です。
より詳しい補償範囲や違いについては、以下のコラムの「サイバー保険の種類」で解説しています。
▼サイバー保険は保険料は月額いくら?料金相場から補償内容、選び方まで徹底解説!
どの保険を選択してよいかわからない場合は、お気軽にご相談ください。

中小企業がサイバー保険に加入するメリット
サイバー保険への加入は、中小企業にとって多くのメリットをもたらします。単に金銭的な補償だけでなく、事業継続を支える様々な効果が期待できます。
経済的損失の補填
サイバー攻撃を受けた場合、システム復旧費用、専門家による調査費用、顧客への賠償金、事業中断による逸失利益など、さまざまな経済的損失が発生します。特に中小企業にとっては、その負担は事業継続に深刻な影響を与えかねません。 実際の事故対応では、以下のような費用が発生するケースがあります。
| 費用項目 | 内容と目安金額 |
|---|---|
| フォレンジック調査費 | 原因・被害範囲の調査 (例)PC10台+サーバ1台 → 約1,300万円 |
| 法律相談費用 | リーガル対応・弁護士費用など → 数十万円~ |
| 広報・謝罪費用 | 新聞広告・DM送付など → 全国紙:240万円前後 |
| コールセンター設置 | 最大3オペ×3か月間 → 約700~1,000万円 |
| システム復旧費用 | データ復元、ITベンダー対応 → ケースにより変動 |
| 再発防止対策費 | セキュリティ強化費・外部支援 → ケースにより変動 |
上記のように、1件のサイバー事故で数千万円規模の損害が発生することも珍しくありません。
実際、中小企業規模においてもフォレンジック調査だけで数千万円を超えるケースや、トータルで1億円超の損害が発生した企業の事例も報告されています。
中小企業にとって、これらの費用は事業継続を揺るがす重大なリスクとなり得ます。
そのため、サイバー保険での経済的補填は極めて重要な対策の一つです。
参考:日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA)「サイバー攻撃を受けるとお金がかかる(インシデント損害額調査レポートより)」
インシデント対応を支える社内体制と外部支援
サイバー攻撃が発生した際、原因調査・被害対応・広報・法的対応など、企業には高度な専門性と迅速な判断が求められます。
本来、こうした対応は以下のような社内組織によって担われることが一般的です。
大手企業では、これらの体制が整備されていることが常識とされ、危機対応力の一環として求められています。
■ CSIRT(シーサート)
セキュリティインシデント発生時に、原因特定から社内調整・再発防止策までを主導する組織横断型の専門チーム。IT・法務・広報等と連携して対応。
■ SOC(Security Operation Center)
24時間体制でシステムやネットワークを監視し、異常を検知・分析する専門組織。外部委託されるケースが多い。
■ BCP対策本部(事業継続計画)
災害等の緊急時の事業継続判断を担う全社的組織。最近ではサイバー攻撃を含む重大リスクへの対策本部として設置されることも多い。
【関連記事】SOC(ソック)とは?役割・CSIRTとの違いと導入形態をわかりやすく解説【中小企業向け】
しかし中小企業ではこうした専任体制を持つケースは稀であり、セキュリティポリシーが整備されておらず、多くは情報システム部門や管理部がその役割を兼任しています。
おそらく突然やってくるサイバー事故への初動対応体制や手順を整備されていないのではないでしょうか。
そのためインシデント発生時に「どうしたらよいかわからない」といった混乱に陥ることも少なくありません。
サイバー保険による対応支援
多くのサイバー保険には、
サイバー保険は保険そのものの機能(保険金)に加え、どの保険会社でも下記のような多くの無料サービスを兼ね備えているため、このサービスをご希望されて加入されるお客様もいらっしゃいます。(※無料サービスの範囲は保険会社によって異なります。その範囲はご相談ください。)
【平時用】※リスク軽減のためのサービス
- サイバー関連の最新情報の提供
- 企業のリスク状況の診断
- 従業員への標的型メール訓練
- 管理職層向けセキュリティ研修
【緊急時用】
- 緊急時ホットラインサービス
- インシデント初動対応アドバイス(被害拡大防止)
- 原因究明、影響範囲調査・広報支援など
- トラブル相談(SNS炎上対策など)
- 法律相談(専門弁護士紹介含む)
- 行政対応支援
保険会社としても、被害の拡大を防ぎたいという立場から、こうした支援体制には積極的です。
専門家のサポートを受けることで、混乱した状況下でも冷静かつ的確な判断と対応が可能となり、被害の最小化と早期解決が期待できます。
なお、これらの支援サービスは保険に含まれている場合もあれば、別途費用が発生するケースもあります。
どこまでの対応が補償対象となるかは保険会社や契約内容によって異なりますので、あらかじめご相談ください。
企業信用の維持と向上
サイバー攻撃による情報漏洩やサービス停止は、顧客や取引先からの信用を大きく損なうリスクがあります。
一度失った信頼を取り戻すには、多大な時間と労力を要することが多く、企業にとっては深刻な経営課題となり得ます。
そうした中で、サイバー保険への加入は、企業がリスクに対して備えていることの具体的な証として、評価されることがあります。
近年では、親会社や取引先が実施するセキュリティチェックの一環として、サイバー保険の加入状況を確認されるケースも増えており、備えの有無が企業の信頼性判断に影響を与えることも少なくありません。
企業信用のポイント整理
- リスクに備える企業として対外評価につながる
- セキュリティチェックで加入有無が確認されることも
- 上場準備・外資系取引で信頼構築の材料に
- 加入を公表しレピュテーション管理に活用可能
- インシデント発生時の迅速対応・被害最小化に寄与
さらに、実際にインシデントが発生した場合でも、保険による支援を活用しながら、迅速かつ誠意ある対応を行うことで、被害の最小化と信用回復につなげることが可能です。
外部からの注目が集まる中で、初動の早さと対応の誠実さが、企業としての姿勢を示す重要な局面となるでしょう。
中小企業がサイバー保険に加入する際のデメリットや注意点
サイバー保険には多くのメリットがありますが、加入を検討する際にはいくつかのデメリットや注意点も理解しておく必要があります。
あらかじめリスクと限界を把握したうえで、自社にとって最適な判断を下すことが重要です。
保険料の負担が発生する
当然ながら、サイバー保険に加入するには保険料の支払いが必要です。
企業の規模、業種、売上高、選択する補償内容、さらにはセキュリティ対策の状況によって保険料は大きく異なります。
中小企業にとっては、こうした保険料が新たな固定費となり、経営を圧迫する要因となることもあります。
限られた予算の中で、保険料が自社のリスクと見合うかどうか、費用対効果の観点から慎重に検討しましょう。
複数の保険会社から見積もりを取り、比較検討することが不可欠です。
すべてのサイバーリスクをカバーできるわけではない
サイバー保険は万能ではありません。
保険商品ごとに補償対象となる事故や損害の範囲が定められており、全てのサイバーリスクをカバーするものではないことを理解しておく必要があります。
たとえば以下のようなケースは、補償対象外となることがあります。
- 戦争やテロに起因するサイバー攻撃
- 企業側の故意または重大な過失による損害
- 法令違反の結果として発生した損害
- 契約時に申告された内容と大きく異なる業務実態があった場合
- ランサムウェア犯に支払う「身代金」そのもの
└ 犯罪組織への資金供与とみなされるおそれがあり
└ 保険業法や公的機関の指針により補償外とされるのが一般的です。
▶ 詳細はこちら:サイバー保険は「身代金」を補償できるのか?
こうした免責項目については、保険証券や約款で明確に定義されています。
契約前に細部まで確認し、自社にとってリスクが高い項目が補償対象になっているかどうかを把握することが大切です。
免責事項や支払い条件の確認が重要
サイバー保険の契約時には、免責事項(保険金が支払われないケース)や保険金の支払い条件を詳細に確認することが極めて重要です。
たとえば以下のような条件が付されていることがあります。
- 被害発生後、一定期間内に保険会社へ通知を行うこと
- (保険会社によっては)警察などの公的機関への届出が必要な場合がある
- 社内における適切なセキュリティ管理体制の有無
- サイバー事故を外部に公表することが保険金支払いの条件となる場合もある
また、保険金には免責金額(自己負担額)が設定されており、損害額がこれを下回る場合は保険金が支払われません。
これらの条件を事前に理解しておかないと、いざという時に期待していた補償が受けられない可能性もあります。
※保険金の支払い対象外となるケースは、これ以外にも多くの取り決めがあります。契約前に必ず確認しましょう。
不明な点は必ず保険会社や代理店に確認し、納得した上で契約を進めましょう。
サイバー事故を外部に公表する件の詳細は、以下のコラムで、支払い条件や事故公表の判断ポイントとして解説していますので、あわせてご確認ください。
▶ 保険金の支払い条件と公表判断についての解説はこちら

中小企業のためのサイバー保険:7ステップで選ぶポイント
サイバー保険は、サイバー攻撃や情報漏えいといった経営リスクに備える有効な手段です。
しかし「種類が多すぎて選べない」「自社に必要な補償がわからない」といった声も少なくありません。
そこで本コラムでは、中小企業がサイバー保険を導入する際に検討すべき7つのステップを、次の2つのフェーズに分けて解説します。
STEP 1:現状把握(ステップ①~③)
まずは、自社のリスク状況や、すでに加入している保険・サービスとの関係を整理します。
このステップを丁寧に行うことで、過不足のない保険選びが可能になります。
STEP 2:保険内容の選定と比較検討(ステップ④~⑦)
次に、必要な補償内容を明確にし、複数の商品を比較しながら、自社に最も合った保険を選ぶフェーズです。
補償範囲・金額・保険料・付帯サービスをバランスよく検討することで、納得感のある保険設計ができます。
それでは順番に見ていきましょう。
① 自社のリスク分析を最初に行う
サイバー保険を選ぶ前に、まず自社がどのようなサイバーリスクに晒されているのかを明確にしましょう。
たとえば、ECサイトを運営している企業では「個人情報の漏えい」、製造業では「工場の制御システムへの攻撃」といったリスクが考えられます。
また、BPO業務や運用代行・委託業務などでクライアントの情報を預かっている企業では、情報漏えいや障害によって、委託元の業務に支障をきたし、損害賠償責任が発生する可能性もあります。
さらに、親会社や取引先とシステム連携している企業では、自社が踏み台となって取引先に不正アクセスされる「踏み台被害」のリスクも。
これは「サプライチェーン攻撃」に近い構造であり、第三者への損害賠償責任が発生する恐れがある点でも重要です。
なお、保険金額の目安を検討する際は、パソコンやサーバの台数、売上規模、インターネット接続されている製造・業務システムの有無なども考慮しましょう。
リスク分析の方法が分からない場合は、お気軽にご相談ください。
②今使っているサービスに「付帯型サイバー保険」があるか確認する
最近では、セキュリティサービスやクラウドサービス、業務ソフト、光回線などにサイバー保険が付帯するケースが増えてきています。
たとえば、WAF提供企業やSaaS型の会計ソフトベンダー、通信キャリアなどが、自社サービスの付加価値として簡易型のサイバー保険を無料で提供していることがあります。
補償内容によっては非常に魅力的な保険が付帯されている場合もあります。
ただし、こうした付帯型サイバー保険の補償範囲は、そのサービスの利用中に発生したサイバー事故に限定されていることが多く、
自社の他システムやネットワーク、従業員の操作ミスによる事故などは補償対象外となるケースがほとんどです。
・光回線に自動付帯されているサイバー保険:光回線を使用している時の事故が補償される。
→ つまり、スマホ使用時やテレワーク先など、別の回線を使っていた場合は補償されない。
・ウイルス対策サービスに自動付帯されているサイバー保険:ウイルスやマルウェアに関する事故のみが対象。
→ 例えば、メール誤送信や不正アクセス、PCの乗っ取りといった事故は補償されない。
特に、付帯保険の補償額は自社のパソコン・サーバの台数や、保有する個人情報の量に対して十分とは限らず、補償範囲や限度額が自社の実態に見合っているかにも注意が必要です。
もし補償が不足していると感じた場合は、付帯保険をベースに、不足分のみを追加で補う設計も可能ですので、状況に応じた見直しをおすすめします。
③他の保険との補償重複を確認する
火災保険や賠償責任保険など、すでに加入している他の保険で一部のサイバーリスクがカバーされている場合があります。
補償内容が重複していると、無駄なコスト負担や想定と異なる支払い条件につながるおそれがあるため、他保険との補償の重複や優先関係を事前に確認しておきましょう。
※【ご注意】以下表は代表的な保険の一例であり、補償内容は保険会社や保険商品やご契約プランによって異なります。
実際の契約内容や補償範囲は、必ずご自身で確認してください。
| 保険種別 | 補償内容(主な部分) | サイバー保険との関係 |
|---|---|---|
| 企業総合賠償責任保険・事業総合賠償責任保険 | 財物損害・利益損失・第三者賠償などを包括的に補償 | 一部プランでサイバー攻撃による損害がカバーされることがある(要確認) |
| 情報漏えい保険 | 個人情報の漏えいに伴う賠償責任・通知費用・見舞金など | サイバー保険の「情報漏えい補償」と重複しやすい |
| 業務過誤保険(E&O保険) | 業務上のミスによる損害賠償責任を補償 | IT業務やBPOにおける事故がサイバー攻撃による場合、補償範囲が重なることがある |
| PL保険(生産物賠償責任保険) | 製品やシステムの欠陥で第三者に損害を与えた場合の賠償 | ソフトウェアの脆弱性等が原因で損害が出たケースと重なる可能性あり |
| 施設賠償責任保険 | 事務所設備の不備による事故への補償 | 通信設備障害等が人身事故に関与した場合など、稀に重なるリスクあり |
| 火災保険・動産総合保険 | 建物・什器・IT機器の損害に対する補償 | サイバー攻撃による物的損害は原則対象外(例外に注意) |
| 損害賠償責任保険 | 顧客や取引先に損害を与えた際の補償(人的・物的) | サイバー原因での損害が対象となるかは商品設計による(要確認) |
④ 補償範囲と補償金額を適切に設定する
①で行ったリスク分析をもとに、どのような損害が発生し得るのかを整理し、補償範囲と補償金額を適切に設定することが重要です。
補償範囲としては、以下のようなリスクが一般的に想定されます。
- 損害賠償責任(情報漏えいや業務停止などによる対外的な賠償)
- 事故対応費用(緊急対応・専門家費用など)
- 利益損害や事業中断補償
- 訴訟・広報対応費用
- データ復旧費用やシステム修復費用
自社のリスク特性に応じて、こうした補償のどこまでをカバーする必要があるのかを検討しましょう。
次に、補償金額の設定です。
補償金額を試算する際には、パソコンやサーバの台数、クラウド利用状況、従業員数などの基本情報も目安になります。
金額が低すぎると実際の被害額をカバーしきれず、高すぎると保険料負担が大きくなってしまうため、事業規模・情報資産の重要度・過去の被害事例などを踏まえ、バランスの取れた設定が求められます。
「3000万円ぐらいでいいかな?」と適当に支払い金額を決めてしまうと、万が一の際に補償が足りないということが起こります。
必要であれば、代理店や保険会社に相談しながら進めるのがおすすめです。
⑤複数の保険会社の商品を比較する
サイバー保険は、損害保険会社各社から様々な商品が提供されています。
それぞれの保険会社が補償内容や保険料、付帯サービスの構成などで特色を打ち出し、競争しているのが実情です。
一社だけの提案で決めてしまうのではなく、複数の保険会社や保険代理店から情報を収集し、提案内容を比較検討することが非常に重要です。
各社の違いを理解した上で、自社のニーズに最も合致する保険を選びましょう。
割引を受けられるかもチェックする
サイバー保険は、セキュリティ診断の実施や多要素認証(MFA)の導入など、一定のセキュリティ対策を講じている企業には、保険料の割引が適用されることがあります。
中には最大で60%の割引を行う保険会社もあります。
保険会社によって割引制度の有無や条件は異なるため、あわせて確認しておくと良いでしょう。
⑥保険料と補償内容のバランスを比較検討する
保険料は重要な選択基準の一つですが、単純に保険料の安さだけで選ぶのは避けるべきです。
安価な保険は補償範囲が限定的であったり、補償金額が低かったり、付帯サービスが十分でなかったりする可能性があります。
・知り合いの会社のシステム保守を請け負っていたが、システムの脆弱性を狙ったサイバー攻撃によりクライアントが個人情報漏洩してしまった。
→ 自社の事故しか補償されないサイバー保険に加入していたため、クライアントは補償対象外だった。
・情報漏洩保険に加入していたが、ランサムウェア攻撃によりシステムやデータが破損。
→ 情報漏洩は補償されたが、データ復旧費用やパソコン・サーバの修理費用や買い替え費用は補償されなかった。
自社に必要な補償内容と補償金額を試算した上で、複数の保険会社の商品を比較し、最もコストパフォーマンスの高い保険を選ぶことが賢明です。
見積もりを取得する際には、同じ条件(補償範囲、補償金額など)で見積もりを依頼すると比較しやすくなります。
もし試算方法が分からない場合は、お気軽にご相談ください。
⑦付帯サービスの内容を確認する
サイバー保険の価値は、保険金の支払いだけではありません。特に中小企業にとっては、インシデント対応支援や平時のサイバーリスク対策支援といった「付帯サービス」の有無と内容が極めて重要です。
インシデント発生時のサービスとしては、24時間365日対応の緊急ヘルプデスクや、フォレンジック調査、法的アドバイス、広報支援などが提供される場合があります。こうしたサービスは、IT専任担当者がいない企業にとって特に有用です。
また近年では、事故発生時だけでなく、平時に活用できるサービスが付帯される保険商品も増えています。たとえば、社内のセキュリティ診断や、標的型メール攻撃訓練、従業員向けの情報セキュリティ教育コンテンツの提供などが含まれることもあります。
これらの付帯サービスは、単体で契約すると数十万円かかるような内容も含まれている場合があり、保険選びの大きな判断材料になります。サービス内容、利用条件、回数制限、追加費用の有無などを必ず確認し、他社商品と比較検討することが大切です。(※無料サービスの範囲は保険会社によって異なります。その範囲はご相談ください。)
【補足】契約後も「見直し」が大切
サイバー保険は、損害保険なため一般的に1年間契約であり、毎年の更新が基本となります。
また、売上高などの事業規模に応じて保険料が変動するため、契約時点と比べて状況が大きく変わった場合には注意が必要です。
IT環境の変化や新たな業務の開始、外部委託先の追加、法改正など、事業環境の変化に応じてリスクも変化します。
契約内容が現在のリスクに対応しているかを定期的に確認し、必要があれば補償内容や保険金額、付帯サービスを見直すことが重要です。
とくに保険の更新時は、補償内容・限度額・付帯サービスの見直しタイミングとして最適です。惰性で継続せず、契約時と現在を比較しながら、必要に応じて再設計を行うことをおすすめします。
まとめ:納得できる保険選びのために
サイバー保険は、企業のリスク対策として重要な役割を果たします。
本コラムで紹介した7つのステップを踏むことで、自社にとって本当に必要な補償を見極め、無駄のない保険選びができるはずです。
とくに中小企業にとっては、現状を正しく把握し、複数の商品を比較したうえで補償内容やサービスを検討することが、納得のいく保険選びのカギとなります。
「安いから」「すすめられたから」といった理由ではなく、自社のリスクに合った備えを選ぶことが大切です。
なお、実際には①のリスク分析の段階で悩んでしまう企業が非常に多く、「どこまで想定すべきか」「何が必要かわからない」といったご相談を多くいただきます。
不安や疑問がある場合は、早めに専門家に相談することで、無駄な遠回りをせずにすみます。
保険代理店は、複数の保険会社の商品を取り扱っており、中立的な立場から自社に合った補償内容を提案する専門家です。
「何をどこまで備えるべきか」「保険料の目安は?」といった疑問にも丁寧に対応いたします。
「何から手をつけてよいかわからない」「ちょっと話だけ聞いてみたい」
そんな段階でも構いません。今の自社にどんな備えが必要か、一緒に確認してみませんか?
お気軽にご相談ください。
サイバー保険の費用相場は?中小企業のケース
「サイバー保険はいくらぐらいかかるの?」という疑問をお持ちの方も多いかもしれません。
しかし、保険料や補償内容の事例を具体的に掲載することは、法律(保険業法)上の制限があります。
誤解を招く説明や、虚偽の案内を避けるため、保険会社の確認を受けた文書でなければ、具体的な金額例を紹介することはできません。
これは、消費者保護の観点から「虚偽のことを告げる行為や誤解を与える表示」を禁じる保険業法に基づく規定です。
(参考:保険業法では、虚偽の説明は禁止されています|そんぽの相談ガイド)
また、法人向けのサイバー保険には、一般的な価格表というものが存在しません。
通常は、企業の年間売上高・業種・セキュリティ体制などを総合的に確認した上で、1年分の保険料をオーダーメイドで見積もる形となります。
その上で、保険会社によって割引制度があり、プランによっては割引をつけることも可能です。(※ 保険会社やプラン、過去の事故有無により異なりますのでお問合せください。)
上記のことからサイバー保険の保険料の「相場」を一律に語ることが難しく、費用の幅も非常に大きくなります。
とはいえ、実際の保険料例を紹介している保険会社もありますので、参考までに下記をご覧ください。
実際の保険料は企業の状況により大きく異なります。
ご自身の会社に適した補償内容・金額の目安を知りたい方は、どうぞお気軽に弊社までご相談ください。
見積もり取得の重要性
自社にとって最適な保険料を知るためには、実際に複数の保険会社や保険代理店に見積もりを依頼することが不可欠です。
見積もり依頼の際には、自社の業種、売上高、実施しているセキュリティ対策などの告知が必要です。
多少手間はかかりますが、複数の見積もりを比較することで、自社のリスクやご予算に合ったサイバー保険が見つかりやすくなります。
ファーストプレイスでは、5社の保険会社の商品を取り扱っており、貴社に最適なプランを過不足なくご提案いたします。
▶ サイバー保険一括見積 ― 最大5社まとめてお見積もり!
さらに詳しく知りたい方は以下をご覧ください。
▶ サイバー保険ガイドはこちら
まとめ
サイバー攻撃のリスクは、企業の規模にかかわらず、現実的で深刻な経営課題となりつつあります。
特に中小企業にとっては、たった一度の被害が事業の継続に大きな影響を与える可能性も否定できません。
大切なのは、まず自社のリスクを正しく把握し、必要なセキュリティ対策を講じた上で、サイバー保険を「備えのひとつ」として検討することです。
本記事でご紹介した選び方のポイントを参考に、ぜひ自社に最適なサイバー保険を見つけ、安心して本業に専念できる環境づくりにお役立てください。
また、サイバー保険は保険会社が用意している脆弱性診断サービスも利用が可能です。
(保険会社のプラン・サービスにより異なります。詳しくはお問合せください。)
ホワイトペーパーでサイバー保険の基礎と選び方をわかりやすく解説。
まずは資料でポイントを押さえてから、社内検討にお役立てください。
▶ サイバー保険 一括見積はこちら(無料)
当サイトを運営する「ファーストプレイス」では、
大手5社のサイバー保険の保険料を、無料で一括比較・見積りいただけます。
- 東京海上日動火災保険株式会社
- 三井住友海上火災保険株式会社
- 損害保険ジャパン株式会社
- あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
- AIG損害保険株式会社
ECサイトやWebサービスを提供している企業様は、IT業務を提供する企業様向けの「IT業務用サイバー保険一括見積サイト」もご検討ください。
よくあるご質問(FAQ)
Q1. サイバー保険だけ加入していれば、セキュリティ対策は不要ですか?
いいえ。サイバー保険はあくまで「リスクに備える手段のひとつ」であり、セキュリティ対策の代替にはなりません。
多くの保険会社は、一定以上のセキュリティ水準が確保されていない場合、保険金の支払いを制限する条件を設けています。
技術的・組織的なセキュリティ対策を行った上での保険活用が基本です。
Q2. サイバー保険にはどんな種類がありますか?
主に以下の3つに分かれます。
一般企業向けサイバー保険:サイバー攻撃や社内ミスによる損害を広くカバー
情報漏えい特化型保険:情報漏えい事故のみを補償
IT業務向けサイバー保険:システム開発・IT請負業務に特化した補償
詳しくは、以下の記事をご参照ください。
▼サイバー保険の種類
Q3. ランサムウェアによる“身代金”の支払いは保険でカバーされますか?
犯人に直接支払う「身代金」そのものは、原則として補償対象外です。
ただし、ランサムウェア対応にかかるコンサルティング費用や復旧費用、事業中断による損失などは、保険商品によって補償される場合があります。
詳しくは、以下の記事をご参照ください。
▶ サイバー保険は「身代金」を補償できるのか?
Q4. 保険料はどのくらいかかりますか?
保険料は、企業の売上規模・業種・セキュリティ状況・希望補償範囲によって異なるため、目安としての金額提示は難しくなっています。
法人向け損害保険には「価格表」が存在しないため、見積もりベースでの提示が原則です。
下記ページでは一部の保険会社が公開している保険料例をご紹介しています。
▶ 三井住友サイバープロテクター|損保ジャパン サイバー保険
Q5. 中小企業でも加入する意味はありますか?
中小企業こそサイバー保険の備えが重要です。
大企業と異なり、インシデント対応の人材や予算が限られているため、被害が事業継続に直結するおそれがあります。
万一のリスクに備え、保険を通じて初動対応や損害補償、専門家支援を受けられる環境を整えることが推奨されます。
参考サイト:
IPA「情報セキュリティ10大脅威 2025」
警察庁「令和5年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」
日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA)「サイバー攻撃を受けるとお金がかかる(インシデント損害額調査レポートより)」
一般社団法人 JPCERT コーディネーションセンター「経営リスクと情報セキュリティ ~ CSIRT:緊急対応体制が必要な理由 ~」