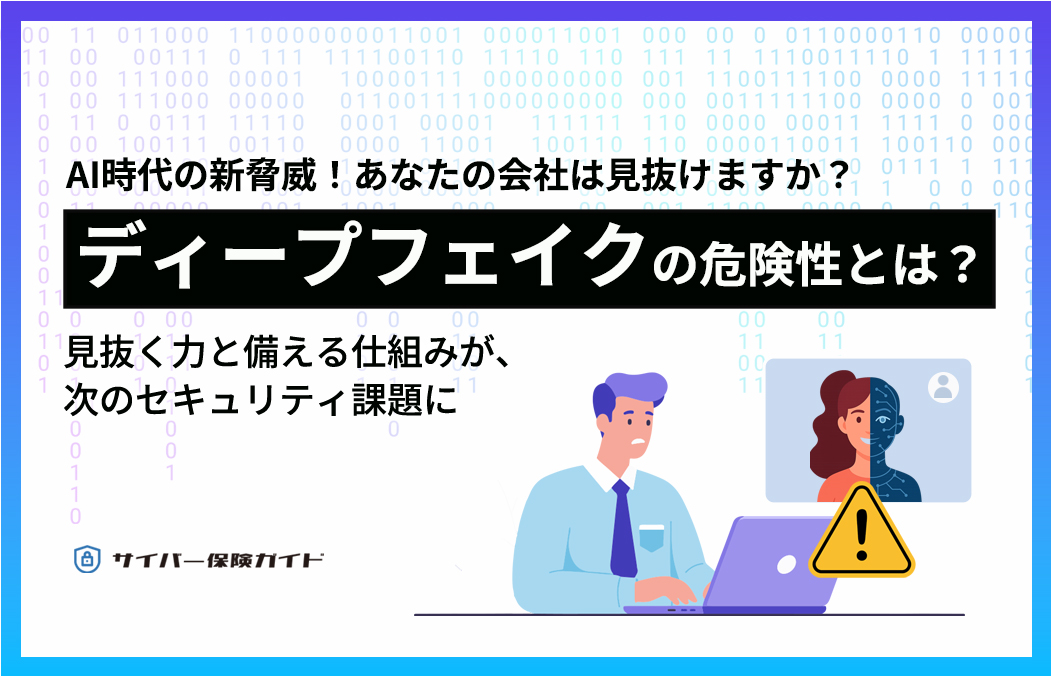
近年、AI技術の進化により、本物と見分けがつかないほど精巧な偽の動画や音声が作成できる「ディープフェイク」が大きな注目を集めています。エンターテインメント分野での活用が期待される一方、その技術が悪用されることによる詐欺や偽情報の拡散といった危険性が深刻な社会問題となっています。
この記事では、ディープフェイクの基本的な仕組みから、具体的な危険性、国内外の悪用事例、そして私たち個人や企業が取るべき対策について、分かりやすく解説します。
ディープフェイクとは?AIが生み出す新たな脅威
近年、AIの進化によって、映像や音声を極めてリアルに作り出す「ディープフェイク」が急速に広まりつつあります。もともとは映像制作や広告などで活用が期待されていた技術ですが、いまでは虚偽情報の拡散や詐欺など、社会に深刻な影響を及ぼす手段として悪用されるケースも増えています。
こうしたディープフェイクの最大の特徴は、「本物と区別がつかないほど自然に見える偽物」を作り出せる点にあります。SNSやニュースを通じて拡散すれば、個人の名誉を損ねたり、組織や社会全体の信頼を揺るがすことさえあります。
この記事では、ディープフェイクの仕組みや生成方法、そしてその裏に潜むリスクを整理しながら、なぜこの技術が「AI時代の新たな脅威」として世界中で問題視されているのかを解説していきます。
関連記事:
情報セキュリティ十大トレンド2025発表:JASAが示す身近な脅威と企業の課題
ディープフェイクの仕組みと特徴
「ディープラーニング」と「フェイク」の組み合わせ
ディープフェイクとは、「ディープラーニング(深層学習)」と「フェイク(偽物)」を組み合わせた造語です。AIが大量の画像や音声データを学習し、特定の人物の顔や声の特徴を再現することで、本人が実際には話していない内容を語っているように見せることができます。こうした技術は、もともと映画や広告などの分野で応用が期待されていましたが、その精度の高さが悪用の温床にもなっています。
本物と見分けがつかない精巧な偽情報の仕組み
この高精度な合成を実現しているのが、GAN(敵対的生成ネットワーク)と呼ばれるAIモデルです。GANは「生成モデル」と「識別モデル」を競わせながら学習させることで、識別が困難なレベルのリアルな偽コンテンツを作り出します。AIが表情の微妙な変化や声の抑揚、光の反射まで再現できるようになった現在では、人間の目や耳では真偽の判断が難しくなっています。SNSや動画投稿サイトを通じて誰でも発信できる環境が整ったことで、ディープフェイクは容易に作られ、瞬く間に拡散される時代になっています。
生成AIとディープフェイクの違いとは?
生成AIは、AIがデータをもとに新しいコンテンツ(文章・画像・音声など)を生み出す技術の総称です。その中でディープフェイクは、主に「既存の人物や映像をリアルに模倣し、偽のコンテンツを生成する技術」を指します。
つまり、生成AIは「技術の広い概念」であり、ディープフェイクはその悪用または特定用途の一部です。
本来、生成AIはクリエイティブ制作や教育などに有用ですが、ディープフェイクのような悪用例が社会的課題として浮上しています。
ディープフェイクの不正利用と4つのリスクとは?
ディープフェイク技術の進化は、私たちの社会に多様な脅威をもたらしています。個人を狙った誹謗中傷や詐欺、企業の信用失墜、さらには政治・社会全体の混乱に至るまで、その悪用の形は年々広がっています。
ここでは、ディープフェイクが不正利用された際に生じる代表的な4つのリスクを整理し、それぞれの具体的な脅威について見ていきましょう。
※以下で示す内容は、ディープフェイク技術が悪用された際に想定される主な被害の例です。実際の事件に限定されるものではなく、社会的・倫理的影響を含めた総合的なリスク分類として示しています。
| リスクの種類 | 主な脅威の内容 |
|---|---|
| 社会の混乱 | 政治家や公的機関の発言を偽装した動画が拡散し、選挙や政策判断に影響を与える。災害時や緊急時に虚偽情報が広まることで、人々の安全や秩序を脅かす。 |
| 金銭的被害 | 企業の関係者や取引先を装った音声・映像が用いられ、従業員に不正送金を指示するなど、ディープフェイクによる詐欺が発生するリスクがある。 |
| 個人の名誉毀損 | 特定の個人の顔や声を用いて虚偽の動画を作成し、人格や信用を損なう。特にポルノ合成(フェイクポルノ)は深刻な人権侵害につながる。 |
| 企業の信用失墜 | 企業や経営者が発言・発表していない内容を偽装した映像が拡散し、ブランドイメージや株価、取引先との信頼関係に悪影響を及ぼす。 |
偽情報の拡散による社会の混乱と世論操作
ディープフェイクは、偽情報を拡散し、社会の信頼基盤を揺るがす危険なツールとなり得ます。例えば、政治家が実際には行っていない発言をしているように見せかけた偽動画がSNSで拡散されれば、世論を誤った方向に導き、選挙の公正性が損なわれるおそれがあります。さらに、災害や感染症などの緊急時に偽の救助情報やデマが流れれば、人々の安全を脅かす事態にもつながります。
情報の発信や共有が容易な現代社会では、真偽を見極める前に情報が拡散されやすく、こうしたリアルな嘘が社会全体の信頼性を損ねる要因となっています。
CEOになりすます詐欺など金銭的な被害
ディープフェイクは、従来のビジネスメール詐欺(BEC)をさらに巧妙化させています。実際に、AIで再現された企業CEOの声を使って経理担当者に電話をかけ、多額の資金を不正送金させた事件も報告されています。
今後は映像通話で顔までも偽装できるようになれば、本人確認はさらに難しくなり、企業は深刻な金銭的損失を被るリスクに直面します。
このような詐欺は、技術的防御だけでは防ぎきれず、組織全体での情報リテラシー教育や確認プロセスの整備が欠かせません。
個人の名誉を著しく傷つける誹謗中傷
ディープフェイク技術の中でも特に悪質なのが、特定の人物の顔をポルノ動画などに合成する「フェイクポルノ」の作成です。これは被害者の人格や社会的信用を深く傷つけ、強い精神的苦痛を与える深刻な人権侵害です。
SNSや動画サイトに投稿された写真や映像が素材として悪用されるケースもあり、誰もが被害者になる可能性があります。一度インターネット上に拡散された動画は、完全に削除することがほぼ不可能であり、被害は長期化する傾向にあります。
企業のブランドイメージ失墜と経済的損失
企業もディープフェイクの標的となっています。役員が不適切な発言をしているように見せかけた偽動画や、製品の欠陥を認めるように仕立てられた映像が出回れば、企業のブランドイメージは一瞬で失われます。こうした虚偽コンテンツは、株価の急落や顧客離れを引き起こし、経済的損失に直結します。
信頼の失墜は一度起これば回復が難しく、現代の企業にとって「評判リスク(レピュテーションリスク)」への備えは、経営上の最重要課題の一つとなっています。
なお、これらは主に直接的な被害に焦点を当てた分類ですが、ディープフェイクの影響はさらに広範です。
報道や司法分野での証拠の信頼性低下、生成AIの倫理的課題、国家安全保障への波及など、社会全体の信頼基盤を揺るがしかねないリスクとしても懸念されています。
次節では、それぞれの危険性を具体的な事例を交えて詳しく見ていきます。
【事例】ディープフェイクが悪用された国内外のケース
ディープフェイクによる被害は、すでに世界中で現実のものとなっています。ここでは、報道などで確認されている国内外の悪用事例を紹介し、その手口と影響の深刻さを具体的に見ていきます。こうした実例を知ることは、今後どのような対策が求められるのかを考える上で重要です。
海外CEOの声を悪用した巨額の送金詐欺
2019年、英国のエネルギー関連企業で、ディープフェイク音声を悪用した詐欺事件が発生しました。詐欺グループは、親会社のドイツ人CEOの声をAIで精密に模倣し、部下である英国子会社のCEOに電話をかけて送金を指示。被害者は信じ込んでしまい、約22万ユーロ(当時のレートで約2,600万円)を詐欺師の口座へ送金してしまいました。
この事件は「ディープフェイクが現実の企業犯罪に悪用された初期の実例」として広く報じられ、AI音声を利用したビジネスメール詐欺(BEC)の危険性が一気に注目されるきっかけとなりました。音声だけでなく、今後は映像通話での偽装も進むとみられ、企業の本人確認プロセスの見直しが急務とされています。
参考:
Sophos News「Scammers deepfake CEO’s voice to talk underling into $243,000 transfer」
ITRC「First-Ever AI Fraud Case Steals Money by Impersonating CEO」
著名人の顔を利用した偽の投資勧誘広告
SNS上では、著名人が特定の金融商品や暗号資産、投資サービスを推奨しているように見せかけた偽広告が相次いでいます。日本でも前澤友作氏や堀江貴文氏などの顔や名前が無断で使われ、AIで加工した映像や音声によって「本人が推奨している」と誤認させる手口が確認されています。実際には本人とは無関係で、詐欺業者が著名人の信頼を悪用して投資サイト等へ誘導するものです。 こうした偽広告の横行については、国会(第213回質問主意書)でも取り上げられ、政府が正式に警戒を表明しています。答弁書では、警察庁や消費者庁が連携してSNS上の虚偽広告や投資詐欺に対応していることが明記され、ディープフェイク技術を利用した新たな詐欺手法として、社会的な対策強化が求められています。 また、これらの省庁は消費者に向けても注意喚起を行い、SNS広告や動画の真偽を安易に信じないよう呼びかけています。とくに「広告内の著名人の発言や推薦は本物か」「出典元が公式アカウントか」を確認し、少しでも不自然であれば拡散せず、プラットフォームの通報機能を利用することが重要です。参考:
衆議院 第213回国会 質問主意書第3205号「AI技術を悪用した詐欺等に関する質問主意書」
@niftyセキュリティ「「前澤さんから投資の誘い…?」それ詐欺です!被害急増中の『SNS型投資詐欺』、その巧妙な手口とは」
INTERNET Watch「有名人の画像を悪用した広告が氾濫中、LINEで連絡すると投資詐欺に誘導されるケースも」
生成AIを悪用した著名人フェイク画像事件 ― 全国初の摘発
2025年10月、警視庁は、生成AIを使って実在の女性芸能人に酷似した画像を作成・販売していた会社員の男性を逮捕しました。報道によると、SNSなどに投稿された写真をもとに、AIで著名人の顔を再現した偽画像を生成し、オンライン上で販売していたとされています。
この摘発は、生成AIを悪用した著名人フェイク画像事件として全国初の事例とされ、社会的な関心を集めました。
警察当局は、本人の許可なく顔や姿をAIで生成することは肖像権や人格権の侵害にあたるおそれがあると警鐘を鳴らしています。
このような事案は、著名人だけでなく一般のSNS利用者にも影響を及ぼす可能性があります。わずかな写真データからもリアルな偽画像や動画を生成できる時代になったことで、「誰もが無意識のうちに被写体にされるリスク」が高まっています。
企業としても、社員や経営層の写真・動画が悪用されることでブランドや信頼性を損なうリスクがあります。自社コンテンツの出所証明(電子透かし)や広報リスク対応の仕組みを整備し、AI技術の悪用に備える姿勢が求められます。
参考:
TBS NEWS DIG「生成AIで女性芸能人を模したわいせつ画像を作成・販売か 会社員の男を逮捕」
毎日新聞「生成AIで著名人模した“性的ディープフェイク”摘発は全国初」
選挙結果に影響を与えかねない政治家の偽動画
ディープフェイクは政治の世界でも深刻なリスクをもたらしています。米国や東南アジアの選挙では、特定の候補者が不適切な発言をしているように見せかけた偽動画が拡散され、投票行動や世論形成に影響を及ぼす可能性が指摘されています。
たとえば2020年の米大統領選やインド、ナイジェリアなどの選挙では、偽情報動画やAI生成音声がSNS上で急速に拡散し、選挙管理委員会が注意喚起を行う事態となりました。こうした「映像を使った世論操作」は、民主主義の根幹である公正な選挙を脅かす危険な手段として、国際的にも規制や監視の対象となりつつあります。
参考:
Journalist’s Resource「How AI deepfakes threaten the 2024 elections」

巧妙なディープフェイクを見分けるためのポイント
ディープフェイク技術は日々進化しており、もはや人の目だけで完全に見破ることは難しくなっています。それでも現在の技術にはまだ微妙な違和感が残る場合があり、注意深く観察することで偽物だと気づけるケースもあります。
ここでは、動画や音声に潜む不自然な特徴と、見抜くための実践的なポイントを紹介します。
| チェック項目 | 確認すべき不自然な点 |
|---|---|
| 顔の動き | まばたきの回数が極端に少ない、または全くない。表情の変化が乏しい。 |
| 顔の輪郭 | 顔と首の境界線がぼやけている、または輪郭が不自然。 |
| 肌の質感 | 肌が滑らかすぎたり、部分的に質感が異なる。 |
| 音声と口の動き | 口の動きと音声がわずかにずれている、または発音が不自然。 |
| 映像の品質 | 顔の一部だけ解像度が異なる、不自然な影や光の反射がある。 |
表情やまばたきの不自然さを確認する
ディープフェイク動画では、人間らしい表情の自然な動きが再現しきれないことがあります。特に、まばたきの頻度が極端に少なかったり、表情が一定で感情の変化が乏しかったりするケースは要注意です。感情に対して表情の変化が乏しい、あるいは動作が硬い場合も、AI生成による映像の可能性があります。人間の表情には微細な筋肉の動きやタイミングのずれが伴いますが、AIはそれを完全に再現できていません。映像と音声のズレや違和感に注意を払う
音声のトーンや抑揚、感情表現にも注目しましょう。声が平板で、感情のこもらない発話が続く場合や、発音に微妙な遅れがある場合は不自然です。また、映像上の口の動きと音声がわずかにずれている「リップシンクのズレ」は、ディープフェイク検出でよく指摘される特徴です。再生速度を下げて確認すると、こうしたズレに気づけることがあります。
ディープフェイク検知ツールの活用を検討する
AI技術の進歩により、個人の目だけで見分けるのはますます難しくなっています。そこで、ディープフェイクを自動で検出するAIツールの活用が注目されています。これらのツールは、映像データ内の微細なピクセルの不整合や、AI生成特有の周波数パターンを解析して、加工された可能性を判定します。
企業では、SNS上の投稿や広告素材を検証する仕組みにこうした検知技術を組み込み、誤情報の拡散やブランド毀損のリスクを軽減する取り組みが進みつつあります。一般利用者も、信頼できるサービスが公開している検知サイトやブラウザ拡張機能を活用することで、自らの目を補完できます。
個人でできるディープフェイクへの対策
ディープフェイクの脅威は、もはや他人事ではありません。私たち一人ひとりが、日々の生活の中で被害に遭わないようにするだけでなく、意図せず加害者にならないための意識を持つことが重要です。SNSの利用や動画の視聴、情報の拡散といった日常的な行動が、思わぬ被害やトラブルにつながることもあります。ここでは、個人レベルで実践できる基本的な対策を紹介します。
SNSで目にする情報の真偽を常に疑う
ディープフェイクの拡散は、多くの場合SNSや動画共有サイトから始まります。衝撃的な映像や有名人の発言を見たときこそ、まず一呼吸おいて確認する姿勢が大切です。「クリティカル・シンキング(批判的思考)」を意識し、その情報が本当に信頼できるものか、発信元が正当なメディアや公的機関かを確かめましょう。少しでも不自然だと感じた場合は、複数の信頼できるニュースソースで同じ内容が報じられているか確認することが効果的です。
特にSNSでは、拡散速度が速いため、一度誤った情報が広がると訂正が追いつかないことがあります。拡散前の冷静な確認が、フェイク被害を防ぐ最初の一歩です。
オンライン上での安易な個人情報の公開を控える
ディープフェイクは、もとになる画像・映像・音声データが多いほど精巧に作られてしまうという特徴があります。SNSや動画投稿サイトに自分の顔写真や音声を不用意に公開すると、悪意のある第三者に素材を提供してしまうことになりかねません。プロフィール画像や公開範囲を定期的に見直し、プライバシー設定を適切に管理することが重要です。また、音声アプリやオンライン会議の録画データなども、外部共有には注意が必要です。日常的な「少しの注意」が、自分の情報を守る大きな防波堤になります。
不審なコンテンツを安易に拡散しない
ディープフェイクは、人の心理的な反応を利用して拡散されることが多いと言われています。怒りや驚きを引き起こす映像ほど拡散されやすく、結果として偽情報が短時間で社会に広まります。真偽が不確かな投稿や、誰かを中傷する内容の動画を見つけた場合は、軽い気持ちで「いいね」や「リポスト」「シェア」を押さないようにしましょう。あなたの一回の操作が、偽情報の拡散や名誉毀損の拡大につながる可能性があります。不審なコンテンツを見かけた際は、プラットフォームの通報機能を活用し、冷静に対応することが大切です。
さらに、SNSアカウントの多要素認証(MFA)設定や、真偽を検証できるオンラインツールの活用も有効です。もし自分や知人の映像が不正に使われた場合は、削除申請や証拠保全を早急に行い、警察や関連機関への通報を検討しましょう。こうした初期対応の意識を持つことが、被害拡大の防止につながります。
企業が講じるべき組織的なディープフェイク対策
ディープフェイクは、企業の信用や資産を脅かす重大なセキュリティリスクです。従業員個人への注意喚起だけでなく、組織全体として体系的に備えることが不可欠です。技術・人・組織の三方向からバランスよく対策を講じることで、被害を防ぐだけでなく、万が一の際にも迅速に対応できる体制を築くことができます。ここでは、企業が取り組むべき主要な対策について解説します。| 対策のカテゴリ | 具体的な実施内容 |
|---|---|
| 技術的対策 | ディープフェイク検知システムの導入、メール送信ドメイン認証(DMARC)の強化、コンテンツの信頼性を証明する電子透かし技術の利用。 |
| 人的対策 | 全従業員を対象としたセキュリティ教育の実施。特に経理担当者や役員秘書など、詐欺やなりすましの標的になりやすい職務への重点的な注意喚起。 |
| 組織的対策 | ディープフェイクを含むサイバー攻撃を想定したインシデント対応計画(CSIRTの役割分担など)の策定と定期的な訓練。 |
電子透かしなどコンテンツの信頼性を担保する技術を導入する
企業が発信する公式な動画や画像に、人間の目には見えない「電子透かし」情報を埋め込む技術を活用することも効果的です。これにより、コンテンツが本物であること、そして改ざんされていないことを証明できます。最近では、AdobeやMicrosoftなどが参加するコンテンツ認証の取り組みと、その技術仕様である C2PA(Content Provenance and Authenticity)が整備され、画像や動画の来歴情報を付与・検証する仕組みが広がりつつあります。こうした技術を導入することで、消費者が安心して情報を受け取れる仕組みを提供でき、企業ブランドの信頼性向上にもつながります。
関連記事
横行するフィッシング詐欺。なりすまし偽サイトを防ぐ企業の対策方法とは?
従業員へのセキュリティ教育を定期的に実施する
ディープフェイクを用いた詐欺の多くは、従業員の心理的な隙を突いて発生します。特に、上司や経営層を装った「音声なりすまし」や「映像送金指示」など、権威を利用した手口が増加しています。そのため、全従業員に対してディープフェイクの危険性や実際の手口を理解させるセキュリティ教育を定期的に実施することが重要です。
加えて、経営層や経理担当者など、金銭・承認プロセスに関わる職務に対しては「送金指示は必ず二重確認する」など、実践的なルールを徹底する必要があります。社内で「疑って確認する文化」を醸成することが、被害防止の鍵となります。
関連記事:
従業員のセキュリティリテラシーを高めるには?本当に効果的な情報セキュリティ教育のポイントを解説
有事の際のインシデント対応計画を策定する
ディープフェイクによる攻撃は、企業のブランドや株価に直接影響を与える可能性があります。被害を最小限に抑えるためには、事前の備えとしてインシデント対応計画を策定しておくことが不可欠です。計画には、広報、法務、情報システム、人事など関係部署の役割を明確に定め、事実確認から情報開示、関係機関への報告までの流れを具体的に定義しておく必要があります。
また、年に一度程度の訓練を行い、緊急時の初動がスムーズに行えるようシミュレーションしておくことが望まれます。迅速で正確な初期対応は、企業の社会的信頼を守る上で極めて重要です。
関連記事:
サイバー攻撃発生時/危機管理だけで事業継続できますか?「デロイト トーマツ 不正リスク調査白書 Japan Fraud Survey 2024-2026」のご紹介
ディープフェイクに関する国内外の法規制と今後の動向
ディープフェイクの脅威が世界的に認識される中、その作成や拡散を抑制するための法整備が各国で進められています。技術の進化に法律が追いつくのは容易ではありませんが、被害者を保護し、悪用を防ぐための取り組みが加速しています。ここでは、日本を含む各国の動向と今後の課題を見ていきます。日本国内における名誉毀損罪などの適用
現時点で日本には「ディープフェイク罪」のような直接的な規制は存在しません。しかし、ディープフェイクによる被害は既存の法律で処罰対象となる場合があります。例えば、他人の名誉を傷つける偽動画を作成・公開した場合には刑法第230条の「名誉毀損罪」が適用され、性的な内容を含む場合は「わいせつ物頒布等の罪」や「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(いわゆるリベンジポルノ防止法)に問われる可能性があります。
また、2024年以降は政府が生成AIを含む「偽情報対策」に関する包括的な検討を進めており、総務省・法務省が連携してガイドライン整備を進めています。
特に、ディープフェイクを用いた詐欺・選挙妨害・誹謗中傷などへの法的対応が課題とされており、今後は特定分野ごとの個別規制が議論される見通しです。
EUや米国で進む規制強化の動き
海外では、日本よりも早い段階から法的枠組みの整備が進んでいます。EUでは2024年に成立した「AI法(AI Act)」により、ディープフェイクを含む生成AIコンテンツには「AIで生成された旨を明示する義務」が定められました。これにより、画像や動画、音声などがAI生成である場合はユーザーに明示する必要があり、透明性の確保を目的としています。
米国でも州レベルで法整備が進行中で、テキサス州やカリフォルニア州などでは、選挙妨害を目的としたディープフェイク動画の公開を禁止する法律が施行されています。また、ディープフェイクポルノの作成や拡散を禁じる法も複数の州で制定され、違反者には刑事罰が科されるようになりました。さらに連邦レベルでも、AIによるなりすましや偽情報発信への包括的な規制法案が議論されています。
技術の進化と法整備の継続的な必要性
ディープフェイク技術は、今後も急速に進化を続けると見られています。映像や音声だけでなく、リアルタイム通信やメタバース空間でのなりすましなど、新しい形態の悪用も想定されています。こうした状況に対応するためには、法律だけでなく、技術的な認証手段の普及や国際的なルール作りも重要です。国や企業、そして私たち個人が連携し、法的規制・技術対策・教育啓発の三つの柱で多角的に取り組むことが求められます。
ディープフェイク問題は単なる法令違反にとどまらず、社会全体の「情報の信頼性」を揺るがす課題であるため、今後も国際的な協調と法整備の継続が不可欠です。
まとめ
ディープフェイクは、私たちの社会に利便性をもたらす一方で、詐欺や偽情報の拡散、名誉毀損といった深刻な危険性をはらむ技術です。その脅威から身を守るためには、個人としては情報の真偽を慎重に見極める姿勢を持ち、企業としては組織的なセキュリティ対策を講じることが不可欠です。とくに企業においては、万が一ディープフェイクを利用した詐欺や風評被害が発生した場合、金銭的な損失だけでなく、取引先や顧客との信頼関係にも大きな影響を及ぼします。こうした予期せぬリスクに備えるためには、技術的な防御に加えて、事後対応を支援するサイバー保険の活用も有効です。
サイバー保険は、被害調査や専門家対応、広報費用など、サイバーリスク全般への対応を幅広く補償するものです。社内の体制整備と併せて、リスクマネジメントの一環として検討することで、より実効的な備えとなるでしょう。
技術の進化に対応しながら、社会全体で情報リテラシーを高め、万一の損害にも強い体制を構築していくことが、今後の重要な課題です。
▶ サイバー保険 一括見積はこちら(無料)
当サイトを運営する「ファーストプレイス」では、
大手5社のサイバー保険の保険料を、無料で一括比較・見積りいただけます。
- 東京海上日動火災保険株式会社
- 三井住友海上火災保険株式会社
- 損害保険ジャパン株式会社
- あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
- AIG損害保険株式会社
ECサイトやWebサービスを提供している企業様は、IT業務を提供する企業様向けの「IT業務用サイバー保険一括見積サイト」もご検討ください。
参照元:
European Commission「AI Act enters into force」
European union「REGULATION (EU) 2024/1689 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL」
Wikipedia「ディープフェイク」
総務省「令和6年版 情報通信白書の概要」
TBS NEWS DIG「
サイバー保険を選ぶ際は、
大手保険会社の中で比較、
検討することをおすすめします。
大手保険会社の中で比較、
検討することをおすすめします。
当サイトの運営会社ファーストプレイスでは、下記5社のサイバー保険を取り扱っています。
サイバー保険を扱う大手メガ損保5社の保険料を無料で一括見積もり・比較いたします。
サイバー保険を扱う大手メガ損保5社の保険料を無料で一括見積もり・比較いたします。
- 取り扱いのある保険会社
- 東京海上日動火災保険株式会社
- 三井住友海上火災保険株式会社
- 損害保険ジャパン株式会社
- あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
- AIG損害保険株式会社












