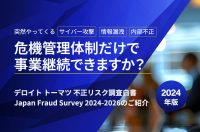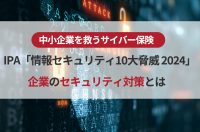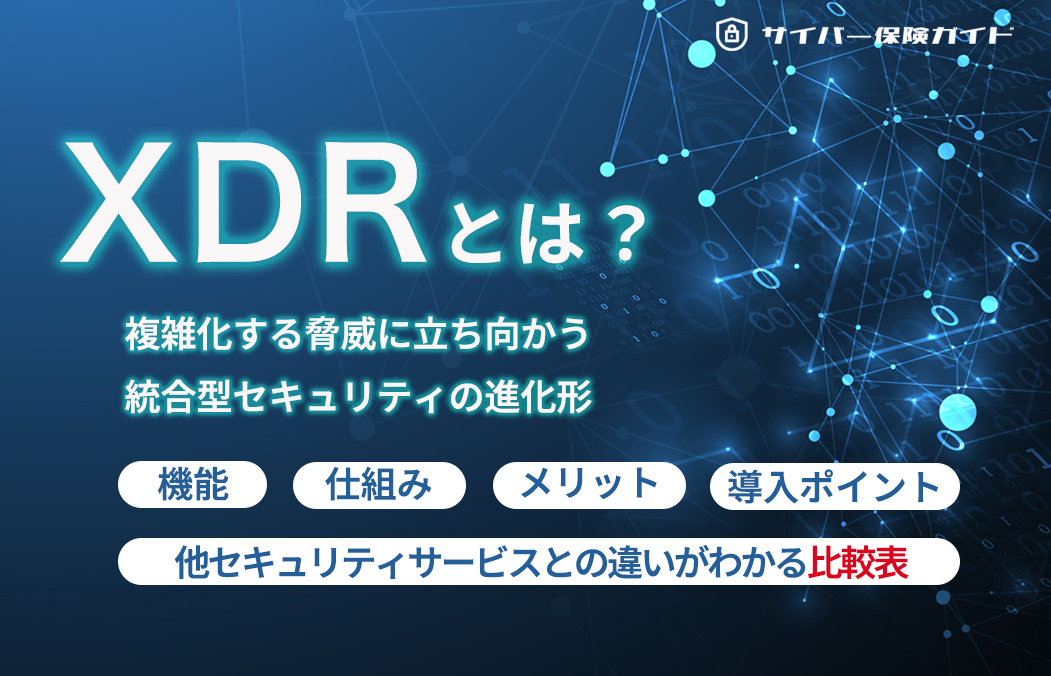
企業が取り扱うデータの量や種類が増え続けるなか、サイバー攻撃の手口も巧妙化し、従来型のセキュリティ対策だけでは十分に守りきれない状況が生まれています。
そこで注目されているのが、エンドポイントからネットワーク、さらにはクラウド環境まで幅広く監視できるXDR(Extended Detection and Response)の仕組みです。
本記事ではXDRの基本から求められる背景や他ソリューションとの違いなどについて、解説します。
XDRとは
XDR(Extended Detection and Response)は、複数領域から発生するセキュリティ情報を包括的に収集し、脅威の検知や分析、対処を一元管理できるようにしたソリューションです。エンドポイント、ネットワーク、クラウドなど、企業が利用しているさまざまな箇所のログを横断的に解析することで、単一の視点では見落としがちな侵入経路や攻撃の痕跡を早い段階で発見できる点が大きな特徴となります。
XDRが求められる背景
企業や組織のIT環境が複雑化し、サイバー攻撃があらゆる角度から同時多発的に仕掛けられる状況に対応するためにXDRの導入が注目されています。ここからは、XDRが求められる背景について、いくつか解説します。
サイバー攻撃の高度化・多様化
XDRが求められる背景として、サイバー攻撃が高度化・多様化していることが挙げられます。たとえば、ランサムウェアは身代金を要求するだけでなく、暗号化したデータを人質にとったり、さらには情報漏えいの脅しをかけたりといった悪質な手口が確認されています。
こうした攻撃は、メールの添付ファイルやネットワーク経由の脆弱性攻撃などの複数の侵入口を用いるため、一部の防御ソリューションだけでは侵入を完全に阻止できず、インシデント発生後の被害拡大を防ぐことも難しくなっています。
このようにクラウドサービスの活用やリモートワークの導入などに伴って守るべきポイントが格段に増えているため、XDRのような総合的な視点で脅威を検知・防御できる仕組みが求められています。
ランサムウェアについての詳細は、下記の記事をお読みください。
▼「組織化、ビジネス化するランサムウェア攻撃」とは?サイバー犯罪の新たな脅威を解説
既存対策の限界とゼロトラストとの関連
XDRが求められるもう1つの背景は、既存対策の限界とゼロトラストとの関連が挙げられます。企業が長らく利用してきたEDRやSIEMなどの製品は、それぞれが得意とする領域の監視や分析を行うには効果的です。
しかし、攻撃者がネットワーク上のさまざまな経路から侵入し、ステルス的に動く場面が増えるにつれて、単独のツールだけで異常を正確に把握し、かつ迅速に対応し続けるのは難しくなっています。
こうした複雑な攻撃シナリオを防ぐうえで、社内外のネットワーク境界を信頼せず、すべてのアクセスを常に検証し続けるゼロトラストの考え方が重要視されています。
ゼロトラストを導入する場合、ネットワークやエンドポイント単位での検知・防御だけでなく、あらゆるレイヤの情報を総合的に分析する必要があります。この点で、XDRはゼロトラストのコンセプトと非常に相性が良いといわれており、組織全体のセキュリティレベルを向上させるための有力な選択肢となっています。
XDRの機能・仕組み
XDRは複数のセキュリティ製品やログを統合し、攻撃の“入口から出口”までを一貫してモニタリングできる点が大きな特徴です。企業内部のネットワークだけでなく、クラウドやリモートワーク環境におけるデータの流れも可視化できるため、潜在的な脅威を早期に捉えて必要なアクションを素早く行えるようになります。
ここからは、XDRの主な機能を4種類ほどご紹介します。
1.データ収集・可視化
XDRが強みを発揮するのは、ネットワーク機器やエンドポイント、クラウドサービス、さらにはメールゲートウェイなど、異なるソースから集まる膨大なログやイベント情報を一元的に収集・分析できる点です。従来は各セキュリティ製品がそれぞれ別の管理画面やログ分析ツールを持っていたため、担当者は必要な情報を横断的に照らし合わせるのに手間をかける必要がありました。XDRによってそれらが集約されることで、管理者は「いつ、どの端末がどんな通信を行い、どのようなファイルにアクセスしたのか」といった全体像をより正確に把握できます。
2.脅威検知
XDRは各種ログを取り込むだけでなく、AIや機械学習を使った高度な脅威検知機能を備えています。具体的には、正常な通信パターンから大きく外れた動きがあった際に自動でアラートを上げたり、既知のマルウェアが使用する通信先やファイル特性を照合したりといった仕組みが用いられます。こうした機械学習モデルは、組織内で日常的に生じるデータの特徴を学習することで、未知の攻撃手法にも柔軟に対応できます。
3.アラート統合
また、多数のアラートが同時発生する状況においても、一元管理されていれば本当に危険度の高いものを優先的に処理できるという利点があります。運用担当者がバラバラのツール画面を行き来しながら手作業で精査する負担は非常に大きいため、こうしたアラート統合の仕組みはセキュリティオペレーション全体の効率を高めるうえで欠かせません。
4.自動対応と封じ込め
XDRの導入が注目される大きな理由の一つに、検知した脅威に対する自動対応や封じ込めを強化できる点があります。例えば、疑わしいプロセスが端末上で動き出した際にはネットワークから切り離す、あるいは特定のIPアドレスとの通信をブロックするといったアクションがシステムによって即座に行われます。もっとも、自動化する範囲をどこまで広げるかは企業によって異なるため、導入時には十分な検証が必要です。適切にルールが設定されていれば、誤検知による業務停止といったリスクを最小限に抑えながらも、深刻な被害が生じる前の段階で攻撃を封じ込めるようになります。
※XDRの自動封じ込め機能は、製品や設定内容によって対応範囲が異なる場合があります。 導入に際しては、自社のリスク対応方針に基づき、対応可能なアクションや自動化のレベルを事前に検証・確認をおすすめいたします。

他のソリューション(EDR・NDR・SIEM)との違い
既存のセキュリティ対策として導入される手法やサービスには、それぞれがカバーする範囲や得意とする領域があります。XDRはこうした点を総合的に補完し、複数のソリューションを一元化するアプローチをとるため、導入前にそれぞれの特徴を理解しておくことが非常に重要です。EDRとの違い
EDR(Endpoint Detection and Response)は、エンドポイント、すなわちPCやサーバー、モバイル端末などに対する脅威を検出し、対応することに特化したソリューションです。エンドポイント上の不審な挙動を検知すると、必要に応じて隔離やプロセスの停止などを実行できるため、ピンポイントな防御としては非常に有効です。
一方、XDRはエンドポイントだけでなく、ネットワークやクラウドの監視まで一括して行う点に大きな強みがあります。EDRが端末個々の挙動を追跡して深く調査するのに対し、XDRはそこから得られる情報を他の領域のログとつなぎ合わせ、より広範囲の脅威を可視化して包括的に対応するイメージです。
NDRとの違い
NDR(Network Detection and Response)は、ネットワークトラフィックを監視し、異常な通信や不審な挙動を捉えることに重点を置いたソリューションです。ファイアウォールやIDS/IPSといった従来のネットワークセキュリティ製品と比べて、振る舞い検知にフォーカスした解析を行うため、従来型の境界防御だけでは見過ごされがちな内部ネットワークでの不審な活動を早期に検知できる点が特徴です。
ただし、NDRだけではエンドポイント上の詳細な挙動やクラウド環境での情報はカバーしきれません。ネットワーク上の通信を解析することが主目的であるため、端末側で起きているプロセスの異常やクラウド上の設定不備などは、見つけるまでに時間がかかる可能性があります。
XDRはネットワークとエンドポイントだけでなく、クラウド環境やその他のセキュリティ製品から得られるログも広範囲に取り込み、脅威の連鎖をいち早く検知します。
SIEMとの違い
SIEM(Security Information and Event Management)は、さまざまなシステムやセキュリティ製品のログやイベントを一元管理し、相関分析を行うためのプラットフォームです。SIEMは、ログやイベントの一元分析を通じてサイバー攻撃の前兆を捉えることを目的に、多くの企業に導入されています。
ただし従来のSIEMはあくまで分析に特化した製品が主流であり、脅威を発見した後の対応は、別途EDRやファイアウォールなどのソリューションに任されるケースが一般的でした。
しかし近年では、SOAR(Security Orchestration, Automation and Response:セキュリティ運用自動化)と連携することで、一定の自動的な封じ込め機能を実現するSIEM製品も市場に広がりつつあります。
対して、XDRはSIEMのように複数のログを統合・分析するだけでなく、検知した脅威に対する迅速な封じ込めや対処までを自動化できる仕組みを備えています。
クラウドやエンドポイントなど、各種防御手段を統合的に制御するオーケストレーション機能を持つため、アラートが発生した際にも、セキュリティ担当者が手作業で対応する負担を最小限に抑えることが可能です。
なお、XDRやSIEMは製品ごとに対応範囲や機能に差があるため、名称だけで判断せず、自社の目的や運用方針に応じて慎重に選定することが重要です。
一口情報:他セキュリティ対策との違いを整理
「XDRを導入すれば、他のセキュリティ製品は不要なのか?」という疑問をお持ちではないでしょうか。各製品はそれぞれ目的や役割が異なり、補完し合う関係にあります。
以下に、XDRとよく比較される用語・製品との違いをまとめました。
XDR・EDR・NDR・SIEM・SOC・MDR・WAF・CASBの違い比較表
| 用語 | 主な役割 | 守る対象 | XDRとの関係 |
|---|---|---|---|
| XDR | 横断的な脅威検知・対応を自動化 | エンドポイント・ネットワーク・クラウド等 | 中核的な統合プラットフォーム |
| EDR | エンドポイント(デバイス等)の不審挙動を検知・対応 | PC・サーバ等の端末 | XDRに内包 or 連携されることが多い |
| NDR | ネットワークトラフィックの異常検知 | 社内外ネットワーク | XDRに統合されることがある |
| SIEM | ログの一元分析・相関検知 | 全システムのイベントログ | 分析基盤として似ているが目的が異なる |
| SOC | セキュリティ監視・運用体制 | 組織内外のすべて | XDRを活用して監視業務を効率化できる |
| MDR | 外部による監視・分析・対応代行 | 対象は企業全体 | XDRをベースにサービス提供されることが多い |
| WAF | Webアプリへの攻撃をブロック(入口防御) | Webサーバ・アプリケーション | XDRとは目的が異なるが併用が望ましい |
| CASB | クラウド利用の可視化と制御 | SaaS、IaaS、クラウドアプリ全般 | XDRとは別の領域。クラウドの安全管理に特化した補完的ソリューション |
【選定ポイント②】各種セキュリティソリューションは、共通名称であっても製品ごとに機能や連携範囲が大きく異なる場合があります。XDR・SIEMともに、最新型では自動対応機能を備える製品もあり、導入にあたっては機能比較・PoC(検証導入)を行ったうえでの選定が重要です。
WAFについての詳しくは下記記事をお読みください。
▼WAFとは?仕組み・種類・メリット・選び方をわかりやすく解説【企業向けセキュリティ対策】
XDR導入によるメリット
XDRの活用によって期待できるのは、単なる脅威検知能力の向上だけでなく、業務やビジネスを継続するうえで欠かせないリスク低減やコスト削減といった、経営面のメリットにも及びます。ここでは、XDRがどのようにして組織のセキュリティ水準を高め、運用効率や企業の信頼を向上させるのかを具体的に解説します。検知・対応スピードの向上
XDRを導入すると、脅威を検知した際の全体的な対応スピードが飛躍的に向上する可能性があります。たとえば、従来型のソリューションだと、端末上の感染を発見してからネットワーク通信の遮断や他の端末への拡散状況を調べるまでに時間がかかり、その間に被害が拡大するリスクが高まりがちです。XDRでは検知と同時にネットワーク層やクラウド上のアクセス状況が可視化されるため、どの端末から感染が始まり、どこへ広がりそうなのかを即座に把握でき、被害の深刻化を防ぎやすくなります。こうしたタイムラインを短縮する仕組みが整備されることで、インシデント発生から封じ込めまでの間に攻撃者が自由に活動できる余地が減り、事態をより早期に収束させられるのです。
運用負荷の軽減とコスト効率
XDRのメリットには運用担当者の負荷を軽減し、コスト効率を高める効果も挙げられます。複数のセキュリティツールを同時に扱っていると、異なる管理画面やレポートを行き来するだけで業務時間の大部分が費やされてしまい、結果的に重大なアラートを見落とすリスクも増大します。
XDRによってアラートの分析や対処が一つのコンソール上で行われるようになると、オペレーションの無駄が減り、人的リソースをより重要度の高いタスクに振り向けられるようになります。
コスト面でも、ツールを個別に導入し、運用担当者がその都度切り替えながら管理する場合に比べて、XDRを活用した統合的な仕組みのほうが全体的なランニングコストを圧縮できる可能性があります。
XDR導入の流れとポイント
XDRは多機能かつ広範な領域をカバーするソリューションであるため、導入にあたっては自社の課題や運用体制をしっかりと見極めたうえで進めることが重要です。ここでは、XDRを導入する際に検討すべき代表的なステップを紹介します。
【ステップ①】自社課題の整理
まずは、自社のセキュリティ環境における課題やリスクを明確にします。「EDRは導入済だがクラウドやメールは未対応」「インシデント対応に時間がかかっている」など、現状を可視化することが出発点となります。
【ステップ②】要件定義・対象範囲の明確化
どの領域(エンドポイント・クラウド・ネットワーク・メール等)をXDRの対象とするかを定めます。また、自動対応の範囲や、どのようなアラートを検知対象とするかについても整理しておく必要があります。
ポイント:導入にあたっては、既存のEDRやSIEM、WAFなどとの連携可否や重複機能の整理も事前に確認しておくと、導入後の混乱を避けられます。
【ステップ③】PoC(検証導入)の実施
いきなり本番導入せず、まずはスモールスタートでXDRの効果を確認します。実際の検知精度や誤検知の有無、操作性や運用への影響などを検証し、自社環境に合った製品かを見極めましょう。
【ステップ④】運用体制の整備
XDRは導入して終わりではなく、「検知→対応→振り返り」の流れを回すことが重要です。社内のセキュリティ監視・対応チームやMDRサービス(外部の専門会社に監視・分析・初動対応をアウトソースできるセキュリティサービス)などとの連携、アラート対応フロー、レポートの共有体制など、運用面の準備も並行して進めます。
【ステップ⑤】本番導入と継続的な改善
本格運用を開始した後も、アラート内容や封じ込め対応の有効性を定期的に確認し、ルールや自動対応設定のチューニングを行います。XDRは運用を重ねるほど精度が向上し、組織全体のセキュリティレベルを高めることができます。
まとめ:XDRとサイバー保険の組み合わせで総合的なセキュリティ戦略を
XDRは、高度化・多様化するサイバー攻撃に対応するうえで、導入時の体制整備や連携設計を慎重に行えば、コスト効率や事業継続の観点で大きな利点をもたらします。さらに、サイバー保険との組み合わせも検討することで、企業の経営リスクを一層低減する総合的なセキュリティ戦略が実現できるでしょう。
セキュリティとサイバー保険については、下記記事をお読みください。
▼法改正でサイバー保険義務化の可能性はある?企業のセキュリティ対策とあわせて解説
企業は社会的責任をもって適切なセキュリティ対策を取り、サイバー攻撃に備えなければなりません。
しかし、残念ながらサイバー攻撃や情報漏えいのリスクをゼロにすることは難しいため、万が一の事故に備えた対策も必要です。
サイバー保険に加入しておけば、万が一の際に生じる多大な経済的損失や労力から自社と従業員を守ることができます。この機会に検討してみてください。
▶ サイバー保険 一括見積はこちら(無料)
当サイトを運営する「ファーストプレイス」では、
大手5社のサイバー保険の保険料を、無料で一括比較・見積りいただけます。
- 東京海上日動火災保険株式会社
- 三井住友海上火災保険株式会社
- 損害保険ジャパン株式会社
- あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
- AIG損害保険株式会社
ECサイトやWebサービスを提供している企業様は、IT業務を提供する企業様向けの「IT業務用サイバー保険一括見積サイト」もご検討ください。