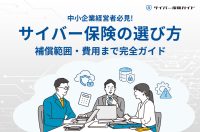企業のシステムやWebサービスを安全に保つためには、「脆弱性診断」と「ペネトレーションテスト(侵入テスト)」という2つのアプローチがあります。
この2つは混同されがちですが、目的や手法が全く異なります。適切な対策を講じるためには、両者の違いを正確に理解し、自社の状況に合わせて最適なテストを選択することが不可欠です。 本記事では、企業のセキュリティ担当者様に向けて、ペネトレーションテストと脆弱性診断の違いを5つの観点から分かりやすく解説します。
脆弱性診断とペネトレーションテストの基本的な違い
よく比較されが「脆弱性診断」と「ペネトレーションテスト」ですが、どちらもシステムの弱点を確認する検査ですが、「診断」は予防、「テスト」は実戦を想定した評価です。脆弱性診断はシステムの「健康診断」、ペネトレーションテストは「実践的な模擬戦闘」と考えると理解しやすいでしょう。
脆弱性診断とは?
脆弱性診断とは、サーバーやWebアプリケーション、OS、ネットワーク機器などに存在する既知の脆弱性(セキュリティ上の弱点)を網羅的に検出する検査です。この診断の目的は、攻撃される前に問題を洗い出し、早期に修正することです。
いわば人間ドックや健康診断のように、システム全体を定期的にスキャンして潜在的なリスクを特定し、重大な障害が起こる前に対応策を講じることを目指します。
一般的には、脆弱性スキャナー(※注1)などの自動ツールを用いて、公開されている脆弱性情報(CVEやOWASP Top10など)(※注2)に照らし合わせてチェックを行い、設定ミスや古いソフトウェアなどの問題を検出し、検出結果を専門家が確認・報告します。
この診断は、セキュリティテストの初期段階 と位置づけられ、システム導入前や運用中の定期メンテナンス時に実施することが推奨され、テスト結果は組織の脆弱性管理や改善計画の基礎資料として活用されます。
| 分類 | 主な対象 | 概要 | 主なツール例 |
|---|---|---|---|
| ネットワークスキャナー | サーバー・ネットワーク機器 | OSや通信ポート、設定の脆弱性を検出(例:SSH設定ミス、古いApacheなど) | Nessus、Qualys、Rapid7 Nexpose |
| Webアプリケーションスキャナー | Webサイト・Webアプリ | フォーム入力などを自動チェックし、XSS・SQLインジェクション等を検出 | OWASP ZAP、AeyeScan、Vex |
| ホストスキャナー | OS・ソフトウェア | パッチ未適用・古いバージョンを特定し、更新管理を支援 | OpenVAS、Qualys、Tenable.io |
| クラウド構成スキャナー | AWS・Azure等の設定 | アクセス権や公開設定の誤りを検出し、クラウド環境の安全性を確認 | Prisma Cloud、AWS Inspector |
※ 自動スキャンは「既知の脆弱性パターン」を検出するため、ゼロデイ脆弱性や設計上の論理的欠陥は対象外です。
IPAおよびNISTでは「自動診断+専門家によるレビュー」の併用を推奨しています。
CVE(Common Vulnerabilities and Exposures) は、世界中で報告されたソフトウェアの脆弱性に識別番号を付与する国際的な仕組みです。
例:CVE-2024-12345 のように管理され、危険度(CVSSスコア)や対策が各国データベース(NVD、JVNなど)で公開されます。
OWASP Top 10 は、Webアプリで特に多い脆弱性を10種類にまとめた国際指標です。
「アクセス制御の不備」「暗号化の失敗」「インジェクション」など、実際の攻撃データに基づき数年ごとに更新されています。
NIST SP 800-115 “Technical Guide to Information Security Testing and Assessment”
IPA『安全なウェブサイトの作り方(改訂第7版)』第7章「脆弱性診断」
ペネトレーションテストとは?
ペネトレーションテスト(Penetration Test:侵入テスト)とは、専門家が攻撃者の視点に立ち、実際の攻撃シナリオをもとにシステムへの侵入を試みる検査です。脆弱性診断で発見された問題や既知の脆弱性を踏まえつつ、「実際に悪用できるのか」「侵入後どこまで被害が拡大するのか」を実証的に検証します。
このテストの目的は、防御の実効性を確認し、組織の防御力・検知能力・対応力を総合的に評価することです。
単に脆弱性の有無を調べるだけでなく、攻撃が成功した場合の影響範囲や検知体制の有効性までを確認する点が特徴です。
テスト結果は、組織の防御体制の強化や、サイバー攻撃対応の訓練にも活用されます。
そのため、単なる診断では見落とされがちな設定ミス・運用上の盲点・多層的な連鎖リスクを把握できる点が特徴です。
近年では、より実践的な攻撃を再現する「レッドチーム演習(※注3)」や「ブルーチームとの対抗演習(※注4)」に発展しています。
レッドチーム演習は、攻撃者の立場から実際のサイバー攻撃を模倣し、組織の防御力や検知体制を評価する訓練です。
NIST SP 800-115で定義されるペネトレーションテストの考え方をさらに発展させたもので、英語ではRed Team Exercise(レッドチーム演習)と呼ばれます。
単に脆弱性を発見するのではなく、組織がどれだけ早く異常を検知し、効果的に対応できるかを検証する点に特徴があります。
攻撃は長期間にわたるシナリオ形式で行われ、標的型攻撃や内部侵入など現実的な手法を用いる場合もあります。
ブルーチームは、防御側(SOCやCSIRTなど)として、レッドチームの攻撃を検知・遮断・報告する役割を担います。
この防御訓練はBlue Team Exercise(ブルーチーム演習)と呼ばれ、実際の攻撃を想定して対応力を高めることを目的としています。
また、攻撃と防御の両チームが同時に活動する形式をRed vs Blue Exercise(対抗演習)と呼び、組織全体のセキュリティ対応力と連携体制を実戦的に検証する取り組みとして注目されています。
NIST SP 800-115 “Technical Guide to Information Security Testing and Assessment”
PCI SSC “Penetration Testing Guidance” v1.1
IPA「情報セキュリティ10大脅威」関連解説
【比較表】脆弱性診断ペネトレーションテストの違いを5つの観点で比較
「脆弱性診断」と「ペネトレーションテスト」は、どちらもセキュリティ上の弱点を明らかにする検査ですが、
目的や手法、費用、実施頻度などの観点で大きく異なります。
ここでは、5つの観点から違いを整理して比較してみましょう。
| 5つの観点 | 脆弱性診断 | ペネトレーションテスト |
| 1.目的 | 脆弱性の網羅的な検出 | 侵入の可否と影響範囲の確認 |
| 2.手法と範囲 | ツールと手動によるシステム全体のスキャン | 攻撃者視点のシナリオベースによる侵入試行 |
| 3.費用 | 比較的安価(数十万円~) | 比較的高価(数百万円~) |
| 4.期間 | 短期間(数日~数週間) | 長期間(数週間~数ヶ月) |
| 5.実施頻度 | 定期的(年1回以上、仕様変更時など) | 不定期(必要に応じて実施) |
違い1:目的
脆弱性診断の目的は、システムに存在する脆弱性を網羅的に発見し、早期に把握することです。
これにより、潜在的なリスクを洗い出し、重大な障害や攻撃の発生を未然に防ぐことを目指します。
一方、ペネトレーションテストの目的は、発見された脆弱性をもとに「実際に侵入できるか」「侵入後にどのような被害が発生しうるか」を検証することです。
単に弱点を見つけるだけでなく、攻撃を受けた際の影響範囲や防御の有効性を実証的に評価します。
【比較まとめ】
脆弱性診断の目的:システム全体に潜む脆弱性(セキュリティ上の弱点)を網羅的に発見すること
ペネトレーションテストの目的:発見された脆弱性をもとに、実際の攻撃を再現して「侵入できるか」「侵入後どこまで被害が拡大するか」を実証的に確認すること
つまり、脆弱性診断は「リスクの洗い出し」、ペネトレーションテストは「リスクの実証と評価」に重点を置いている点が大きな違いです。
違い2:手法と範囲
脆弱性診断では、診断ツールと専門家による手動検査を組み合わせ、対象システム全体をスキャンします。
既知の脆弱性リストやセキュリティデータベース(CVE、OWASP Top10など)をもとに、設定ミスや古いソフトウェアの利用状況などを確認します。
ペネトレーションテストでは、攻撃者の思考や行動を模倣し、事前に設計された攻撃シナリオに基づいて侵入を試みます。
対象はシステムだけでなく、従業員を狙った標的型メールなど、人的要素を含むケースもあります。
【比較まとめ】
脆弱性診断:ツールと専門家による網羅的なスキャンで弱点を抽出する
ペネトレーションテスト:攻撃シナリオに基づき、実際に侵入を試行して防御の有効性を確認する
つまり、脆弱性診断は「広く浅く」チェックする調査型、ペネトレーションテストは「深く掘る」実証型のアプローチといえます。
違い3:費用
一般的に、ペネトレーションテストは脆弱性診断よりも高額になります。
脆弱性診断が数十万円から実施できるのに対し、ペネトレーションテストは専門家による綿密な計画・実施・報告を要するため、数百万円以上になるケースもあります。
【比較まとめ】
脆弱性診断:比較的安価(数十万円〜)
ペネトレーションテスト:比較的高価(数百万円〜)
つまり、脆弱性診断は「定期点検」目的、ペネトレーションテストは「本格的な安全検証」目的として、コストの考え方が異なります。
違い4:期間
脆弱性診断は、対象システムの規模にもよりますが、数日〜数週間程度で完了します。
一方、ペネトレーションテストはシナリオ設計や侵入試行などに時間を要するため、数週間〜数ヶ月に及ぶ場合もあります。
【比較まとめ】
脆弱性診断:短期間(数日〜数週間)で完了
ペネトレーションテスト:長期間(数週間〜数ヶ月)を要する
つまり、脆弱性診断はスピード重視、ペネトレーションテストは精度重視のテストといえます。
違い5:実施頻度
脆弱性診断は、システムの改修・アップデート時、あるいは定期的なセキュリティ点検として年1回以上の実施が推奨されます。
一方、ペネトレーションテストはすべてのシステムで毎回行うものではなく、重要システム導入時やセキュリティ対策レベルを総合的に評価したい場合など、必要に応じて実施されます。
【比較まとめ】
脆弱性診断:定期的(年1回以上、仕様変更時など)
ペネトレーションテスト:不定期(重要システム導入時など、必要に応じて実施)
つまり、脆弱性診断は「継続的なメンテナンス」目的、ペネトレーションテストは「戦略的な検証」目的で行われる点が異なります。

どちらを選ぶべき?ケース別に見る最適なテストの選び方
脆弱性診断とペネトレーションテストは、目的や範囲が異なるものの、どちらもサイバー攻撃からシステムを守るために欠かせない検査です。
では、自社ではどちらのテストを実施すべきなのでしょうか。
ここでは、ケースごとにおすすめの選び方を紹介します。
脆弱性診断がおすすめのケース
次のような場合は、まず脆弱性診断の実施を検討しましょう。
- Webサイトやサービスを新規に公開する前
- システムのアップデートや仕様変更を行った後
- 定期的なセキュリティチェックをこれまで実施したことがない
- 予算を抑えつつ、基本的なセキュリティリスクを把握したい
サイバー攻撃の多くは、すでに知られている脆弱性を悪用するものです。
まずは脆弱性診断で基本的な弱点を洗い出し、対策を講じておくことがセキュリティ強化の第一歩となります。
ポートスキャンとは?初心者でもわかる!仕組み・被害事例・対策をわかりやすく解説
ペネトレーションテストがおすすめのケース
一方で、以下のような企業や状況では、より実践的なペネトレーションテストが効果的です。
- 金融機関や医療機関など、機密性の高い情報を扱っている
- 既にWAF・IDS/IPSなどのセキュリティ対策を導入済みで、有効性を実証したい
- インシデント対応体制(CSIRT)の実効性を訓練・評価したい
- 事業継続にサイバー攻撃が深刻な影響を与える重要インフラを運営している
基本的なセキュリティ対策を講じた上で、さらに上位レベルの防御力や体制の強度を確認したい場合に、ペネトレーションテストは大きな効果を発揮します。
【関連記事】「組織化、ビジネス化するランサムウェア攻撃」とは?サイバー犯罪の新たな脅威を解説
脆弱性診断の進め方
脆弱性診断は、システムに潜む弱点を効率的かつ網羅的に把握するための基本プロセスです。
単にツールでスキャンするだけでなく、診断の範囲設定や結果の活用方法までを含めた「リスクマネジメント活動」として進めることが重要です。
以下では、一般的な3つのステップと、その目的・実務ポイントを紹介します。
ステップ1:対象のヒアリングと計画策定
まず、診断対象となるシステムの範囲・構成・目的をヒアリングします。
これにより、診断の目的と優先順位(例:外部公開サーバー/クラウド環境/アプリケーションなど)を整理し、最適な診断計画を立てます。
主な確認ポイント:
・対象システムの構成図、利用OSやアプリケーションのバージョン
・ネットワークやクラウド設定(アクセス制御・公開範囲)
・診断期間、稼働影響の有無、報告書の希望フォーマット
この工程でのヒアリング精度が、診断の品質を大きく左右します。
ステップ2:診断の実施
計画に基づき、診断ツールと専門家の手動操作を組み合わせて検査を行います。
Webアプリケーション、ネットワーク、OS、データベースなどを対象に、既知の脆弱性情報(CVE・OWASP Top10 など)と照合しながら問題点を抽出します。
自動スキャンでは見逃されがちな論理的脆弱性(例:アクセス制御の不備、業務ロジック上の欠陥)についても、専門家による手動確認が行われます。
ステップ3:報告と改善提案
診断の結果は、発見された脆弱性の一覧に加え、それぞれの重要度・影響範囲・推奨対策が整理された報告書として提出されます。
報告書は、開発チームへのフィードバック資料としてだけでなく、経営層へのリスク説明資料や、サイバー保険加入・更新時のエビデンスとしても活用可能です。
改善対応を行った後は、再診断(リテスト)によって修正の有効性を確認するのが望ましいとされています。
脆弱性管理とは?企業が今取り組むべき理由と始め方をわかりやすく解説
ペネトレーションテストの進め方
ペネトレーションテストは、攻撃者の視点に立ってシステムへの侵入可否を検証する、より実践的なセキュリティ評価です。
単に脆弱性を見つけるのではなく、「攻撃を受けたときにどこまで防げるか」「侵入されたらどこまで影響が及ぶか」を可視化し、組織の防御力と対応力を高めることを目的としています。
ここでは、一般的な3つのステップをもとに、実施プロセスと押さえておくべきポイントを紹介します。
ステップ1:シナリオ設計と準備
まず、テストの目的と範囲を明確にし、攻撃シナリオを設計します。
「どのような攻撃者が、何を狙って、どのように侵入を試みるか」を具体化することで、現実的かつ実効性のあるテストになります。
主な準備項目:
・対象システムの構成図、認証・通信方式の確認
・想定する攻撃者像(外部/内部、不正アクセス/情報窃取など)
・侵入成功とみなすゴール設定(例:顧客情報へのアクセス、権限昇格、サーバー停止など)
・テスト実施時期と関係部署(開発・運用・CSIRT)との調整
この段階で経営層や関係部門を巻き込み、目的と成果の共有を行うことが、後工程の合意形成をスムーズにします。
ステップ2:テストの実施
シナリオに基づき、ホワイトハッカー(倫理的ハッカー)が実際に侵入を試みます。
攻撃の種類は、外部からのネットワーク侵入、Webアプリケーション経由の攻撃、内部ネットワークからの権限昇格、ソーシャルエンジニアリング(標的型メール)など多岐にわたります。
このテストでは、単に攻撃を成功させることだけでなく、組織の検知・通報・対応体制(CSIRTやSOC)の実効性を評価する点も特徴です。
攻撃をリアルタイムで検知できたか、どのような初動対応が取られたか、といった運用レベルの確認も重要です。
ステップ3:結果の分析と改善提案
テストの結果は、侵入成功の可否に加えて、使用された攻撃経路・影響範囲・検知状況を詳細に分析し、報告書としてまとめられます。
報告書には、組織の防御体制・対応手順・従業員教育を含めた改善提案が盛り込まれます。
結果は一度きりの報告ではなく、今後のセキュリティロードマップや演習(レッドチーム演習/ブルーチーム訓練)に発展させることで、実戦力の強化に活かせます。
サイバー攻撃発生時/危機管理だけで事業継続できますか?「デロイト トーマツ 不正リスク調査白書 Japan Fraud Survey 2024-2026」のご紹介
まとめ:診断とテストを使い分けて、リスクを「見える化」する
脆弱性診断とペネトレーションテストは、どちらが優れているというものではなく、目的とリスクレベルに応じて適切に使い分けることが大切です。
脆弱性診断で弱点を早期に発見し、ペネトレーションテストで実際の攻撃シナリオを想定した防御力を検証することで、組織のセキュリティ対策はより実効性の高いものになります。
しかし、どれだけ技術的な対策を講じても、すべてのリスクをゼロにすることはできません。
万一の情報漏えい・不正アクセス・ランサムウェア感染といった事故が発生した際には、金銭的損失や取引停止、信用失墜といった経営リスクが伴います。
こうした「最後の備え」として有効なのがサイバー保険です。
技術的な防御策で“攻撃を防ぐ”ことに加え、サイバー保険で“被害後の損失を最小化する”体制を整えておくことで、企業のリスクマネジメントはより強固になります。
【関連記事】サイバー保険とは?補償内容・対象範囲・導入メリットをわかりやすく解説
また、保険会社が用意している脆弱性診断サービスも利用が可能です。
(保険会社のプラン・サービスにより異なります。詳しくはお問合せください。)
▶ サイバー保険 一括見積はこちら(無料)
当サイトを運営する「ファーストプレイス」では、
大手5社のサイバー保険の保険料を、無料で一括比較・見積りいただけます。
- 東京海上日動火災保険株式会社
- 三井住友海上火災保険株式会社
- 損害保険ジャパン株式会社
- あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
- AIG損害保険株式会社
ECサイトやWebサービスを提供している企業様は、IT業務を提供する企業様向けの「IT業務用サイバー保険一括見積サイト」もご検討ください。
出典:
- NIST SP 800-115: Technical Guide to Information Security Testing and Assessment
- OWASP:OWASP Top 10 – 2021
- IPA:脆弱性対策情報データベース(JVN iPedia)
- 経済産業省:サイバーセキュリティ経営ガイドライン Ver.3.0
- JPCERT:インシデントハンドリングマニュアル
よくある質問(FAQ)
- Q. 脆弱性診断とペネトレーションテストの違いは何ですか?
-
脆弱性診断は、システムに存在する弱点を網羅的に洗い出す検査であり、主にツールと手動調査を組み合わせて実施します。
一方、ペネトレーションテストは、実際の攻撃を再現して侵入の可否や被害範囲を検証する実証的なテストです。目的が「発見」と「実証」で異なります。 - Q. 脆弱性診断とは何ですか?
-
脆弱性診断とは、サーバーやWebアプリケーション、OS、ネットワーク機器などに存在する既知の脆弱性(セキュリティ上の弱点)を網羅的に検出する検査です。
人間の健康診断のように、システム全体を定期的にスキャンして潜在的なリスクを特定し、重大な障害が起こる前に対応策を講じることを目指します。 - Q. ペネトレーションテストとは何ですか?
-
ペネトレーションテスト(侵入テスト)とは、専門家が攻撃者の視点に立ち、実際の攻撃シナリオをもとにシステムへの侵入を試みる検査です。
脆弱性診断で発見された問題や既知の脆弱性を踏まえつつ、「実際に悪用できるのか」「侵入後どこまで被害が拡大するのか」を実証的に検証します。 - Q. サイバー保険は、ペネトレーションテストや脆弱性診断の代わりになりますか?
-
サイバー保険は、攻撃を「防ぐ」ための手段ではなく、攻撃を受けた際の損害を「補償する」ための備えです。
技術的対策とあわせて導入することで、攻撃前後の両面からリスクを最小化できます。