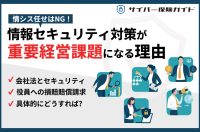セキュリティパッチの重要性は理解していても、実際に企業の現場では「どこまでを対象とすべきか」「誰が責任を持って管理するのか」で悩むケースが少なくありません。
OSや業務ソフトウェアだけでなく、ネットワーク機器やクラウドサービス、さらにはIoT機器まで対象は多岐にわたり、属人化や見落としが起きやすいのが実情です。
本記事では、セキュリティパッチ管理の対象範囲を整理したうえで、企業がどのように体制を整え、役割分担を行うべきかを分かりやすく解説します。
セキュリティパッチそのものの基本から知りたい方は、先に関連記事「セキュリティパッチ管理(前編)|適用しないリスクと重要性、基本の流れも解説」もあわせてご覧ください。
▼本記事は後編です。前編の記事もあわせてチェックしてみてください▼
セキュリティパッチ管理(前編)|適用しないリスクと重要性、基本の流れも解説 https://cyber-insurance.jp/column/2478/セキュリティパッチの対象はどこまで?
「セキュリティパッチ=Windowsや業務ソフトの更新」というイメージを持つ方も少なくありません。しかし、実際には企業においてはIT環境全体に関わる幅広い対象があります。
まずは、どこにパッチが必要なのかを正しく把握しておくことが、運用を成功させる第一歩です。
OSやソフトウェア
もっとも基本的な対象は、WindowsやmacOS、LinuxなどのOS、そして日常的に利用する業務ソフトウェアです。ノートパソコンやデスクトップPCも、OSや業務ソフトの更新を怠れば攻撃の入口となります。
脆弱性が悪用されると、端末やサーバー全体が攻撃にさらされるため、最優先でパッチを適用すべき領域です。
例:Windows 11、macOS、Microsoft Office、Adobe Acrobat、会計ソフトなど
ネットワーク機器やサーバー
ルーター、ファイアウォール、スイッチといったネットワーク機器も重要な対象です。また、メールサーバーやファイルサーバーといった基盤システムも定期的な更新が欠かせません。
例:Ciscoルーター、Fortinetファイアウォール、Windows Server、Exchange Server、NAS機器など
自社ホームページやWebサーバー
会社の公式サイトやECサイトを運営している場合、WebサーバーやCMS(WordPressなど)も忘れてはならない対象です。特に「お問い合わせフォーム」や「資料請求フォーム」、さらに会員サイトや顧客ポータルサイトのログイン画面や入力フォームは、顧客情報を直接扱うため攻撃者に狙われやすい部分です。
脆弱性が残っていると、不正アクセスによる改ざんや個人情報の流出につながる恐れがあります。
外部に公開されている分、攻撃者から狙われやすい領域であるため、こまめな更新とセキュリティ対策が不可欠です。
例:Apache、Nginx、IIS、WordPress、EC-CUBE、各種フォームプラグイン、会員制サイトや顧客ポータルのCMSなど
業務システムや顧客向けシステム
自社で開発・導入した業務システムや、顧客が利用するポータルサイトも対象に含まれます。人事・労務管理システム、請求書管理サービス、名刺管理サービスなど、日常業務に欠かせないシステムはもちろん、業種特有のシステム(例:医療機関の電子カルテ)も定期的な更新が必要です。
例:人事労務管理システム、請求書管理サービス、顧客管理サービス、名刺管理サービスなど
業種特化型システム例:レセプト管理システム、学習管理システム、生産管理システムなど
SaaSやクラウドサービス
クラウドサービスやSaaSは「自動的に更新されるから安心」と思われがちですが、実際には利用者側の設定やバージョン管理が必要な場合があります。特にプラグインや拡張機能を利用している場合は、その部分が脆弱性の原因となるケースもあるため注意が必要です。
例:Dropbox、Google Workspace、Microsoft 365、Slack、Chatworkなど
クラウド基盤(IaaS/PaaS)
AWSやMicrosoft Azure、Google Cloud Platform(GCP)のようなクラウド基盤も重要です。クラウド事業者側でインフラは更新されますが、利用者が構築した仮想サーバーやアプリケーション環境は自社で管理する必要があります。
責任分界点を理解し、自社が担う部分(OSやミドルウェア、アプリケーション)については計画的にパッチを適用することが欠かせません。
例:AWS(EC2、RDS)、Microsoft Azure(仮想マシン、App Service)、Google Cloud Platform(Compute Engine、Cloud SQL)など
モバイルデバイスやIoT機器
スマートフォンやタブレット、さらには社内に設置されたIoT機器(監視カメラやセンサーなど)も見落とされがちな対象です。更新が滞ると、社内ネットワークへの踏み台として利用される可能性があります。
例:iPhone、iPad、Android端末、ネットワークカメラ、スマートプリンター、工場IoTセンサーなど
すべてが「パッチ」で提供されるわけではない
ここまで紹介した対象すべてに、同じ形で「セキュリティパッチ」が配布されるわけではありません。ベンダーから配布されるパッチを適用するものもあれば、SaaSのように提供元が自動更新するケース、AWSなど利用者側で責任を持って更新すべきケース、WordPressのようにバージョンアップで対応するケースもあります。
つまり、対象の種類によって「どのように更新されるのか」を理解しておくことが、管理を進めるうえでの第一歩です。
更新形式の代表的なパターン
– ベンダーが配布するパッチを適用するもの(OS、業務ソフト、ネットワーク機器)
– 提供元が自動更新するもの(SaaS、モバイルアプリ)
– 自社で責任を持って更新・改修するもの(AWS上のサーバー、自社開発システム)
– バージョンアップで脆弱性を解消するもの(WordPressやそのプラグイン、EC-CUBEなどのCMS)
このように対象も提供形態もバラバラであるため、「誰が、どの範囲を、どのように管理するのか」を明確にしないと、漏れや属人化につながります。
こうしたリスクを避けるために不可欠なのが、次章で解説する体制づくりと役割分担です。
パッチ管理には「体制づくり」が欠かせない
セキュリティパッチの適用は、単に技術的な作業を積み重ねるだけでは十分ではありません。対象範囲や更新方法が多岐にわたる以上、誰がどの部分を管理し、どのように責任を持つのかを明確にしなければ、属人化や漏れが必ず発生します。
つまり、パッチ管理を成功させるためには組織としての体制づくりと役割分担が不可欠です。ここからは、その必要性と具体的な考え方を解説します。
なぜ体制が必要なのか
セキュリティパッチの管理を担当者まかせにしていると、属人化や見落としといったリスクが避けられません。たとえば特定の担当者が不在のときに更新が滞ったり、管理対象が漏れたまま放置されたりすれば、脆弱性が残って攻撃の侵入口になってしまいます。
さらに、インシデントが発生した際に「誰が責任を持つのか」が不明確だと、初動対応が遅れ、経営層や顧客への説明も混乱しがちです。
結果として、被害が拡大し、信用失墜や法的責任にも直結する可能性があります。
だからこそ、パッチ管理は属人的な作業ではなく、組織としての体制づくりが不可欠です。
役割と責任の分担を明確にし、計画的に運用することで、更新の抜け漏れを防ぎ、トラブル発生時にも迅速に対応できるようになります。
主な役割と責任分担
パッチ管理を組織として確実に進めるためには、関わる人や部署ごとの役割を明確にしておく必要があります。経営層から現場部門まで、それぞれが自分の立場で責任を果たすことで、初めて継続的かつ安全な運用が可能になります。
経営層・役員の責任
セキュリティパッチの管理は現場の作業に見えますが、実際には経営課題そのものです。経営層や役員は、必要なセキュリティ投資を承認し、パッチ適用を含むセキュリティ対策を全社的な方針として位置づける責任があります。
さらに重要なのは、この責任が法律上の義務と密接に関わっていることです。
会社法では取締役に「善管注意義務(善良な管理者としての注意義務)」が課されており、適切な情報セキュリティ対策を怠った結果として重大なインシデントが発生した場合、経営層が責任を問われる可能性があります。
また、個人情報を扱う企業であれば、個人情報保護法に基づく安全管理措置の不備と判断され、行政処分や損害賠償請求につながるリスクもあります。
つまり、パッチ管理は「情シスの仕事」ではなく、経営層が法的責任を持って監督し、体制を整えるべき領域なのです。
関連記事:
情シス任せはNG!情報セキュリティ対策が重要経営課題となる理由
情報システム部門の役割
情報システム部門は、実務の中心としてパッチ管理を担います。脆弱性情報の収集から適用計画の立案、検証環境でのテスト、本番環境への展開まで、一連の流れを設計・実行するのが役割です。
また、適用状況を記録・可視化し、経営層や監査部門に報告できるようにすることも求められます。
他部門との連携
ただし、情報システム部門だけで全てを完結できるわけではありません。営業部のSFA、マーケティング部門のMA、制作部のCRMなど、各部門はそれぞれの業務システムやクラウドサービスを日常的に利用しているため、安全で実効性のあるパッチ管理を実現するには、社内の各部門との連携が欠かせません。
業務部門との調整
情報システム部門が主体となり、総務や営業、製造などの業務部門と事前に調整し、影響が最小限となるように計画を立てることが重要です。利用部門が協力して作業時間を確保することで、セキュリティと事業継続の両立が可能になります。
現場からのアラート共有
調整はパッチ適用時だけでなく、アラートやエラーメッセージ、挙動の違和感を現場から情報システム部門に迅速に伝える仕組みも必要です。現場の気づきを早期に共有できれば、不具合や適用漏れをすぐに検知し、被害を最小限に抑えられます。
シャドーITの防止
各部門が情報システム部門の承認を得ずにクラウドサービスやツールを独自導入してしまうと、管理対象から漏れ、脆弱性が放置される「シャドーIT」のリスクが生まれます。こうした勝手導入はセキュリティ対策の抜け穴となるため、全社的なルールで禁止し、必ず情報システム部門を通じて導入可否を判断する仕組みを整えることが重要です。
情報システム部門を窓口にすることは、単なる手続きではなく、全社的な統制の一環として欠かせません。

体制を機能させるための運用ポイント
体制を整えるだけでは十分ではなく、実際に運用し続ける工夫がなければ形骸化してしまいます。パッチ管理を実効性のあるものとして継続するためには、仕組みの見える化や自動化に加えて、定期的な見直しや外部の力を取り入れる工夫が欠かせません。
管理台帳やIT資産管理ツールの活用
パッチの適用状況を「見える化」することは、体制を機能させる第一歩です。Excelなどで管理台帳を整備すれば、どの端末に、いつ、どのパッチを適用したのかを一元的に把握できます。
さらにIT資産管理ツールを導入すれば、各端末の状態を自動収集し、一斉配布やレポート出力まで行えるため、管理者の負担軽減と適用漏れ防止に大きく役立ちます。
こうした仕組みは単に便利というだけでなく、監査や経営層への説明責任を果たすうえでも不可欠です。
IT資産管理ツールとは?
IT資産管理ツール(クライアント管理ソフト)は、セキュリティパッチを含めたIT資産全体を効率的に管理するための仕組みを持つシステムツールです。「資産情報の収集」「パッチやソフトの配布」「運用支援(リモート・通知・レポート)」といった、主な3つの機能により、パッチ適用状況を「見える化」するだけでなく、日常的な資産管理や内部統制にも役立つ基盤として機能します。
IT資産管理ツールの種類
IT資産管理ツールにはいくつかのタイプがあり、目的や機能の範囲によって特徴が異なります。たとえば、インベントリやライセンス管理を中心とした「資産管理特化型」、ログ収集やUSB制御など内部不正の防止を重視した「内部統制型」、パッチ配布やウイルス対策を統合した「セキュリティ対策型」などがあります。
また、SaaSの利用状況やアカウントを可視化する「SaaS管理型」、小規模事業者向けの「無料版」も存在します。
導入を検討する際は、まず自社の課題やリスクに照らして必要な機能を見極めることが大切です。 Excel台帳からの移行を段階的に進める場合も、自社の規模やリスクに合った種類を選ぶことで、効率的かつ確実なパッチ管理につながります。
定期的なレビューと教育訓練
体制を維持するには、パッチ管理プロセスを定期的に振り返り、改善点を洗い出すことが欠かせません。例えば「アラートが正しく共有されているか」「適用までに遅れがないか」といった観点で定期チェックを行いましょう。
さらに、現場の従業員への教育も重要です。PCを勝手に再起動しない、エラーメッセージを報告する、といった基本ルールを徹底することで、情報システム部門の負担が軽減され、体制が現場に根づいていきます。
外部パートナーや専門家の活用
すべてを社内リソースだけで対応するのは現実的ではありません。人材や知識が不足している場合は、専門ベンダーによる脆弱性診断やパッチ適用支援を委託したり、CSIRTやセキュリティ専門家の助言を得たりするのが効果的です。
外部の知見を取り入れることで、自社の体制を補強し、限られたリソースでも安定的なパッチ管理を実現できます。
まとめ
セキュリティパッチ管理は、単なる技術的な作業ではなく、組織全体で取り組むべき経営課題です。対象範囲を正しく理解し、明確な体制と役割分担を整え、ツールや外部の知見を活用しながら運用を継続することが、最終的に企業の信頼と事業継続を守ることにつながります。
パッチを「適用するだけ」で終わらせず、定期的なレビューや教育を通じて改善を重ねていくことが、持続的なセキュリティ対策の要です。
いくら体制やツールを整えても、ゼロデイ攻撃など「パッチがまだ存在しない脆弱性」や、適用前に被害を受けてしまうリスクは残ります。
そのため、技術的な対策と並行して、万が一の被害に備える「サイバー保険」によるリスク転嫁を検討することも重要です。
保険を組み合わせることで、金銭的損失や事故対応コストをカバーし、経営への打撃を最小限に抑えることができます。
事故発生後の損害賠償や対応費用に備え、サイバー保険の一括見積で、補償内容を比較・検討しておくことをおすすめします。
特にWebサービス等を提供している企業は、インシデントが起こった際のリスク分散が重要となります。
また、保険会社が用意している脆弱性診断サービスも利用が可能です。
(保険会社のプラン・サービスにより異なります。詳しくはお問合せください。)
▼本記事は後編です。前編の記事もあわせてチェックしてみてください▼
セキュリティパッチ管理(前編)|適用しないリスクと重要性、基本の流れも解説 https://example.com/patch-management-part2▶ サイバー保険 一括見積はこちら(無料)
当サイトを運営する「ファーストプレイス」では、
大手5社のサイバー保険の保険料を、無料で一括比較・見積りいただけます。
- 東京海上日動火災保険株式会社
- 三井住友海上火災保険株式会社
- 損害保険ジャパン株式会社
- あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
- AIG損害保険株式会社
ECサイトやWebサービスを提供している企業様は、IT業務を提供する企業様向けの「IT業務用サイバー保険一括見積サイト」もご検討ください。
参考サイト:
CISA.gov「Understanding Patches and Software Updates」
個人情報保護委員会事務局「ウェブサイトを運営している事業者の皆様への注意喚起」
内閣サイバーセキュリティセンター「政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン」