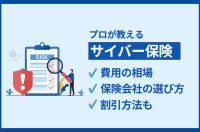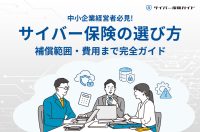近年、企業の大小を問わずサイバー攻撃の脅威は増大しており、中でも「ゼロデイ攻撃」は非常に危険な攻撃手法として知られ従来のセキュリティ対策だけでは防ぎきることが困難といわれています。
この記事では、ゼロデイ攻撃の基本的な仕組みから、企業が取るべき具体的な対策、万が一被害に遭った場合の対処法まで、セキュリティご担当者様に向けて分かりやすく解説します。
ゼロデイ攻撃とは?
ゼロデイ攻撃とは、OSやソフトウェア、ネットワーク機器などに脆弱性が見つかった際に、開発元が修正プログラム(パッチ)を配布する前の段階で、その脆弱性を悪用して行われる攻撃のことです。修正プログラムが存在しない「無防備な期間」に攻撃が仕掛けられるため、検知や防御が難しく、被害が大きくなりやすいのが特徴です。総務省や警察庁も、ゼロデイ攻撃を企業や個人にとって重大な脅威として注意喚起しています。
修正パッチ提供前の「無防備な期間」を狙う攻撃
ソフトウェアの脆弱性が発見されても、開発元が修正プログラムを準備・配布するまでには時間がかかります。その間、利用者は防御手段を持たないままサービスを利用することになり、攻撃者にとっては格好の標的となります。
ゼロデイ攻撃はこの「修正パッチ未提供の期間」を突くため、根本的な防御策が取りづらいのが実情です。
Nデイ攻撃との違いは?
ゼロデイ攻撃に似た言葉として「Nデイ攻撃」があります。ゼロデイ攻撃が「修正プログラムがまだ存在しない段階」で行われるのに対し、Nデイ攻撃は修正プログラムがすでに公開されているのに、利用者がまだ適用していない状態を狙う攻撃です。
ここでいう「N」とは、脆弱性が公表されてから経過した日数を表します。つまり「Nデイ攻撃」とは、「公表から何日経ってもアップデートしていないシステムは狙われる」という意味を含んでいます。
たとえば、あるソフトウェアで脆弱性が見つかり、開発元が修正パッチを公開したとします。ところが利用者が「後でやろう」と放置していたり、自動更新を止めていたりすると、その間は攻撃者にとって利用可能な弱点が残ったままになります。
ゼロデイ攻撃とNデイ攻撃の違いをまとめると、次のようになります。
| 攻撃の種類 | 攻撃のタイミング | 特徴 |
|---|---|---|
| ゼロデイ攻撃 | 脆弱性の修正パッチ提供前 | 対策方法がなく、防御が極めて困難。 |
| Nデイ攻撃 | 脆弱性の修正パッチ提供後 | パッチを速やかに適用することで防御可能。 |
このように、ゼロデイ攻撃は防御が難しいのに対し、Nデイ攻撃は対応が遅れたシステムを狙うため、早めの更新で防ぐことが可能です。
なぜゼロデイ攻撃は危険視されるのか?
ゼロデイ攻撃が特に危険だとされる理由は、予測や防御が難しい点にあります。多くの企業がセキュリティ対策を導入していますが、ゼロデイ攻撃では従来の対策の効果が限定的になり、被害につながりやすい傾向があります。対策が難しく攻撃が成功しやすいから
ゼロデイ攻撃は、まだ公表されていない未知の脆弱性を突いて行われます。そのため、修正プログラム(パッチ)が存在しないのはもちろん、従来型のパターンマッチング方式(既知の脅威情報をもとに検知する方法)のウイルス対策ソフトでは防ぐことが困難です。防御手段が限られるため、攻撃が成功するリスクは通常より高まります。
未知のマルウェアが使われる可能性が高いから
ゼロデイ攻撃では、新たに作られた「未知のマルウェア」が用いられるケースが多くあります。既存のマルウェア対策で検知されないため、侵入を許してしまう可能性が高まります。侵入後は情報窃取やランサムウェア感染など深刻な被害を引き起こす恐れがあります。関連記事:
サイバー攻撃の企業への被害額は?億単位もありえる被害額|2025年最新版を公開
ゼロデイ攻撃の主な手口と流れは?
攻撃者は周到な準備を経てゼロデイ攻撃を仕掛けます。ここでは代表的な攻撃手口と、実際に利用されやすい経路を紹介します。攻撃メールによるマルウェア感染
業務に関係があるように装った件名や本文を使い、悪意のあるファイルを添付したり、不正なWebサイトへ誘導するリンクを記載したりする手口です。特に「標的型攻撃メール」は取引先や関係者を装うことが多く、見分けが難しくなっています。Webサイトの改ざんによる情報窃取
正規のWebサイトに脆弱性があると、攻撃者に改ざんされ、閲覧しただけでマルウェアに感染させられる手口です。ユーザーが気づかないうちにPCがマルウェアに感染し、個人情報や認証情報が盗まれてしまう危険性があります。信頼しているサイトであっても、脆弱性が放置されていれば攻撃の踏み台にされる可能性があります。VPN機器の脆弱性を悪用した侵入
テレワークの普及に伴い、社外から社内ネットワークへ安全に接続するためのVPN機器が広く利用されています。しかし、VPN自体に脆弱性が存在すると、社内ネットワークの侵入口になります。警察庁の調査(2022〜2023年)では、ランサムウェア感染経路の中でVPN機器を悪用したものが最も多く確認されています。既知・未知を問わず脆弱性を放置すれば深刻な被害につながるため、早急な修正が欠かせません。
ゼロデイ攻撃による被害事例
ゼロデイ攻撃は海外だけでなく、日本国内でも実際に発生しています。ここでは、公式に「ゼロデイ攻撃」と認められた国内の代表的な事例を紹介します。研究機関で発生したリモートアクセス機器への攻撃
2024年末、国内の研究機関においてリモートアクセス機器を狙った不正アクセスが確認されました。この脆弱性はメーカーが修正プログラムを提供・公表する前に悪用されており、公式にゼロデイ攻撃として扱われた事例です。被害調査の結果、個人情報が流出した可能性は否定できないとされましたが、発表時点では具体的な被害は確認されませんでした。国家機関でのVPN機器を悪用したゼロデイ攻撃
2023年から2024年にかけて、国内の国家機関に対して複数回のサイバー攻撃が行われました。攻撃はいずれもVPN機器の脆弱性を起点としたもので、その中にはゼロデイ攻撃が含まれていたことが公式に公表されています。攻撃者は内部ネットワークに侵入し、関係者に関する情報や内部文書を窃取するなどの被害が確認されました。まとめ
これらの事例からも分かるように、ゼロデイ攻撃は国内の公的機関においても現実に発生しており、修正プログラムが提供される前の「無防備な期間」に深刻な被害をもたらす可能性があります。企業や組織は、最新の脆弱性情報を常に収集するとともに、EDRや多層防御、脆弱性診断などの仕組みを活用して、ゼロデイ攻撃に備えることが重要です。
ゼロデイ攻撃への有効な対策とは?
ゼロデイ攻撃は、修正プログラムが提供される前の「無防備な期間」を狙われるため、完全に防ぐことは困難です。しかし、複数の対策を組み合わせることでリスクを大幅に低減することが可能です。ここでは、公的機関の指針を踏まえたうえで、実務的に取り組みやすい対策を解説します。
対策1:OSやソフトウェアを常に最新の状態に保つ
OSやアプリケーション、利用しているソフトウェアの更新通知があった場合は、速やかに最新のバージョンにアップデートすることでゼロデイから派生する「Nデイ攻撃」を防げます。基本的かつ重要な対策なためIPAは、修正プログラム(パッチ)が提供されたら迅速に適用することの重要性を繰り返し強調しています。
自動アップデート機能や管理者が組織内の端末の適用状況の一元管理など、プロセスを整備することが不可欠です。
対策2:EDR(Endpoint Detection and Response)を導入する
ゼロデイ攻撃は既知のパターンでは検出できないため、「侵入を前提に監視する」仕組みが必要です。EDRは、PCやサーバーなどのエンドポイント(端末)を常時監視し、感染の兆候を早期に捉えることができます。攻撃を完全に防ぐことはできなくても、被害の拡大を防止する重要な役割を果たします。
参考記事:
EPPとは?|EPPとEDRの違いと連携で実現する強固なエンドポイント防御
NGAV(次世代アンチウイルス)とは?EPP・EDRとの違いを徹底解説
対策3:サンドボックスを活用する
サンドボックスとは、外部から隔離された安全な仮想環境のことです。 メール添付やダウンロードファイルをそのまま開くのは危険なため、メールの添付ファイルやダウンロードしたファイルを、まずサンドボックスと呼ばれる隔離環境内で実行してみることで、未知のマルウェアであっても安全に検出できます。この手法は標的型メールやゼロデイ攻撃対策の現場で広く使われている技術です。対策4:WAFやIPS/IDSなどネットワークセキュリティを強化する
脆弱性を突いた攻撃は、必ずネットワーク経由で仕掛けられます。WAF(Webアプリケーションファイアウォール)はWebサイトへの不正リクエストを遮断し、IPS/IDS(不正侵入防止・検知システム)は侵入を試みる通信を検知・防御します。特にVPN機器は攻撃対象になりやすく、ネットワーク層での防御が不可欠です。参考記事:
WAFとは?仕組み・種類・メリット・選び方をわかりやすく解説【企業向けセキュリティ対策】
対策5:定期的な脆弱性診断を実施する
ゼロデイそのものは検知が難しいですが、自社環境に潜む「既知の弱点」を放置しないことが、ゼロデイ攻撃のリスクを抑える第一歩です。外部の専門家による脆弱性診断を定期的に実施すれば、攻撃者に先を越される前に弱点を把握できます。対策6:従業員のセキュリティ教育を徹底する
どれだけ高度なシステムを導入しても、それを使う人間の意識が低ければリスクは残ります。 不審なメールの添付ファイルを安易に開かない、不用意にリンクをクリックしない、公共のWi-Fi利用時はVPNを使用するなど、基本的なセキュリティルールを全従業員に周知徹底させることでリスクを大きく減らすことができます。参考記事:
中小企業がサイバー攻撃の対象になる理由とは?対策方法も解説
万が一ゼロデイ攻撃を受けたらどうすべきか?
どれだけ対策を講じても、ゼロデイ攻撃の性質上、被害を完全に防ぐことはできません。だからこそ、インシデント発生時にどのように動くかが、被害の広がりを左右します。ここでは、被害を最小限に抑えるための初動対応を整理します。ネットワークから端末をすぐに遮断する
不正アクセスやマルウェア感染が疑われる端末を発見したら、最初に行うべきはネットワークから切り離すことです。LANケーブルを抜く、Wi-Fiをオフにするなど、物理的に通信を遮断することで、攻撃者への情報送信や社内他端末への感染拡大(横展開)を防止できます。これは「被害を止めるための最優先行動」です。セキュリティ担当者へ迅速に報告する
次に、速やかに社内のセキュリティ担当部署や情報システム部門に報告します。その際、「いつ、どの端末で、どのような操作をしたら、何が起きたか」を具体的に伝えることが、原因究明と対策を迅速に進める上で重要です。自己判断でファイルを削除したり、PCを再起動したりしないようにしてください。専門の外部機関へ相談する
自社だけでの対応が困難な場合は、躊躇なく外部の専門機関に相談しましょう。 情報処理推進機構(IPA)の「情報セキュリティ安心相談窓口」や、契約しているセキュリティベンダーのインシデントレスポンスサービスなど、頼れる窓口は複数あります。関連記事:
自社は本当に大丈夫?中小企業の情報セキュリティの重要性
まとめ
ゼロデイ攻撃は、修正プログラムが存在しない未知の脆弱性を突くため、従来のセキュリティ対策では防御が極めて難しい攻撃です。国内でも実際に発生しており、企業や組織にとって事業継続を脅かす大きなリスクとなっています。
しかし、OSやソフトウェアの更新を徹底するといった基本的な対策に加え、EDR(Endpoint Detection and Response)やサンドボックスなどの先進的なセキュリティ技術を組み合わせる「多層防御」によって、被害リスクを大幅に低減することが可能です。
本記事で紹介した対策を参考に、自社のセキュリティ体制を定期的に見直し、必要に応じて外部の専門家の支援も受けながら強化していくことが、ゼロデイ攻撃への最も現実的な備えとなります。
このようにサイバー攻撃のリスクは、企業の規模にかかわらず現実的で深刻な経営課題となりつつあり、中小企業にとっては、たった一度の被害が事業の継続に大きな影響を与える可能性も否定できません。
大切なのは、まず自社のリスクを正しく把握し、必要なセキュリティ対策を講じた上で、サイバー保険を「備えのひとつ」として検討することです。
本記事でご紹介した選び方のポイントを参考に、ぜひ自社に最適なサイバー保険を見つけ、安心して本業に専念できる環境づくりにお役立てください。
▶ サイバー保険 一括見積はこちら(無料)
当サイトを運営する「ファーストプレイス」では、
大手5社のサイバー保険の保険料を、無料で一括比較・見積りいただけます。
- 東京海上日動火災保険株式会社
- 三井住友海上火災保険株式会社
- 損害保険ジャパン株式会社
- あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
- AIG損害保険株式会社
ECサイトやWebサービスを提供している企業様は、IT業務を提供する企業様向けの「IT業務用サイバー保険一括見積サイト」もご検討ください。
参考サイト:
警視庁「令和5年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」
総務省「国民のためのサイバーセキュリティサイト」