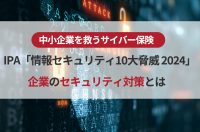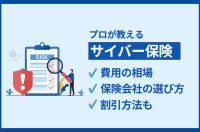企業のウェブサイトやオンラインサービスにとって、サーバーダウンは顧客満足度の低下や売上損失、企業信用の低下など、深刻な影響をもたらすリスクです。 その原因は、アクセスの集中やハードウェアの故障、操作ミス、サイバー攻撃など多岐にわたります。
本記事では、サーバーダウンの主な原因、障害発生時の対応手順、そして予防策までをわかりやすく解説します。安定した運用のために、ぜひ参考にしてください。

サーバーダウンとは何か?よくある症状
サーバーダウンとは、サーバーが一時的または継続的に機能を停止し、ウェブサイトやアプリケーション、業務システムなどのサービスが利用できなくなる状態を指します。
一般的には「サイトがまったく表示されない」「ログインできない」といった深刻な障害が想像されますが、実際には一部の機能だけが使えない、極端に動作が遅いといった状況もサーバーダウンに含まれるケースがあります。
よく見かけるエラー表示の例
サーバーがダウンすると、ユーザーの画面に「404 Not Found」や「503 Service Unavailable」などのエラーメッセージが表示されることがあります。
404 は「指定されたページが存在しない」、503 は「一時的にサービスが利用できない」を意味します。
ほかにも 500 Internal Server Error や 504 Gateway Timeout など、サーバー側の不具合や過負荷を示すステータスコードが出る場合もあり、これらはすべて広い意味でのサーバーダウンと捉えられます。
サーバーダウンの影響はWebサイトに限らず、メールの送受信障害として現れることもあります。SMTPやIMAPといったメール関連のサーバーが正常に機能していない場合、業務上の重要な連絡が滞るおそれがあるため注意が必要です。
一部だけでもサーバーダウン?
「ログインはできるが一部機能だけ使えない」「管理画面だけが落ちている」など、サービスの一部が正常に動作しない状態も、広い意味でサーバーダウンに含まれます。
部分的サーバーダウンの例
- 商品画像が表示されない:ECサイトの商品画像が読み込めず、購入判断ができない状態に。
- 予約フォームだけが送信不可:バックエンドAPIの障害で予約送信が停止し、業務に大きな影響。
- アクセス集中による断続的なタイムアウト:キャンペーン直後に「504」エラー断続発生。
可用性の喪失とは?
ITの専門用語で「可用性(availability)が損なわれている状態」を可用性の喪失と呼びます。これは「ユーザーが必要なときにサービスを使えない状態」を指し、全面停止だけでなく部分障害も含みます。
可用性喪失の具体例
- 商品ページは開くが購入ボタンを押すとエラー → 部分的な可用性喪失
- 管理画面がログインできない → 機能限定の可用性喪失
- サーバーが完全に落ちてアクセス不能 → 全面的な可用性喪失
いずれの場合も、ユーザー体験を損ねる重大なインシデントであり、情報セキュリティの三要素「機密性・完全性・可用性」のうち、可用性が失われた状態といえます。
サーバーダウンがビジネスに与える深刻な影響
サーバーダウンは、ウェブサイトやサービスが一時的に利用できなくなるだけの技術的トラブルではありません。企業活動全体に波及し、金銭面・信頼面・顧客体験の三つの側面で深刻なダメージを与えます。影響の大きさをあらかじめ理解しておくことは、対策に投資する判断材料として不可欠です。1. 金銭的損失と機会損失の発生
サーバーダウンによって発生する最も直接的な影響は、金銭的な損失です。たとえばECサイトで障害が発生した場合、サイト全体が完全に停止していれば、その間の売上は事実上発生しません。
仮に一部の機能(購入手続きやカート操作など)だけが使えない状態でも、ユーザーの離脱や購買中断が生じ、売上の減少につながる可能性があります。
また、企業間の取引システムが一時的に停止した場合には、商談や契約処理が遅延し、タイミングを逃したことによる機会損失も発生します。
さらに、障害の原因調査や復旧作業を外部業者に依頼する場合には、調査費や技術支援費などの追加コストも発生します。自社で対応しきれないトラブルに備えて、外部の専門パートナーとの連携体制を整えておくことも重要です。
参考記事:
サイバー攻撃の企業への被害額は?億単位もありえる被害額|2025年最新版を公開
サイバー保険の保険金の支払い事例・支払いタイミング、支払われない例は?
2. 社会的信用の著しい低下
ウェブサイトやオンラインサービスが頻繁に停止する企業に対して、顧客や取引先は「管理体制が不十分」「信頼できないサービス」と捉えやすくなります。ネガティブな評価がメディアやSNSで拡散すれば、ブランドイメージの低下につながり、一度失った信用を回復するには長い時間と多大な労力が必要です。3. 顧客満足度の低下とユーザー離れ
必要な時にサービスを利用できない体験は、顧客満足度を大きく損ねます。競合サービスが存在する市場では、ユーザーはより安定したプラットフォームへ容易に移行してしまいます。一度離れた顧客を呼び戻すには、割引やキャンペーンなど追加コストが発生し、市場シェアの低下を招く恐れがあります。サーバーダウンは一時的な技術的トラブルにとどまらず、企業活動や信頼、顧客維持にまで影響を及ぼします。万一の際に備え、損失を最小限に抑える体制づくりが重要です。

サーバーダウンの主な原因とは?7つの代表例を解説
サーバーダウンの原因は一つに限定されるものではなく、複数の要因が同時に絡み合っているケースもあります。ここでは、代表的な原因をカテゴリごとに整理し、どのような経緯で障害が発生するのかを解説します。 自社のシステムや運用体制と照らし合わせながら、潜在的なリスクを把握しておくことが大切です。アクセス集中による高負荷状態
テレビ番組での紹介、SNSでの拡散、大規模な広告キャンペーン、人気商品の予約受付や限定商品の販売開始などにより、短時間で大量のユーザーが一斉にウェブサイトへアクセスすることがあります。こうしたアクセス集中により、サーバーの処理能力(スレッド数、メモリ、帯域など)を超えるリクエストが同時に発生すると、処理待ちが発生し、レスポンスが極端に遅くなったり、タイムアウトが多発したりします。
さらに、一定の閾値を超えてリクエストが蓄積すると、サーバーが正常な応答を返せなくなり、最終的にサービス全体が停止状態に陥るおそれがあります。これが、アクセス過多によって引き起こされる典型的なサーバーダウンのパターンです。
例①共用サーバーにおける他サイトのアクセス急増
共用レンタルサーバーやVPS、クラウド型ECシステムなどの環境では、同じ物理サーバー上に複数のユーザー(サイト)が存在します。この場合、自分のサイトではなく、他の利用者のサイトにアクセスが集中しただけでも、CPUやメモリ、ディスクI/Oなどのリソースが奪われ、自サイトが間接的に遅延・ダウンすることがあります。いわば「隣の部屋の騒音で眠れない」ような影響です。
例②マンションのネットワーク帯域の共有による速度低下
なお、これはサーバー側の問題とは異なりますが、閲覧者の通信環境が「マンションタイプの共用インターネット回線」である場合、同じ建物内の他の住人の利用状況によって回線が混雑し、ウェブサイトの表示が遅く感じられることがあります。これはサーバー自体がダウンしているわけではありませんが、ユーザー体験の面では「遅延」や「不具合」と認識されることもあるため、間接的な信頼低下の一因となることがあります。
このように、アクセス集中と一口に言っても、自サイトへの直接的な高負荷と、共有環境ならではの間接的な影響の両面があります。運用中のサーバー環境に応じて、どのリスクが該当するかを把握することが重要です。
ハードウェアの物理的な故障
サーバーは、CPU、メモリ、ストレージ(HDDやSSD)、電源ユニット、マザーボード、ネットワークカードなど、多くの精密部品で構成されています。これらの部品は、経年劣化や温度変化、突発的な物理的損傷などによって故障することがあります。特に回転部品を含むHDDや冷却ファンは消耗が早く、定期的な点検や交換が必要です。一つの部品の障害がサーバー全体の停止を引き起こすこともあるため、ハードウェアの状態管理は重要です。
ソフトウェアのバグや設定不備
OSやミドルウェア、あるいは自社で開発・導入したアプリケーションの中に潜んでいるバグ(プログラムの誤り)が、特定条件下で顕在化すると、サーバーの挙動が不安定になったり、システム全体が停止したりすることがあります。また、設定のミスも大きなリスク要因です。たとえば、アクセス制御の不備やリソース割り当ての誤りなどが原因で、想定外の動作不良が起こることがあります。
悪意のあるサイバー攻撃の脅威
近年、企業を標的としたサイバー攻撃は巧妙化し、サーバーダウンを引き起こす被害も増えています。なかでもDDoS(分散型サービス妨害)攻撃は、膨大なリクエストを不正に送りつけ、サーバーのリソースを使い果たすことで、正規ユーザーの利用を妨げます。さらに、マルウェアの感染によってシステムが破壊されたり、不正アクセスにより重要な設定が改ざんされたりすることもあります。
参考記事:
サイバー攻撃、企業の3社に1社が被害経験【2025年 帝国データバンク調査】― 中小企業も拡大傾向
サイバー攻撃の企業への被害額は?億単位もありえる被害額|2025年最新版を公開
DOS攻撃とは?DDoS攻撃との違い・種類・企業の対策方法まで解説
予期せぬ人的ミスによるトラブル
どれだけ堅牢なシステムでも、運用にあたる人のミスによって障害が発生することがあります。たとえば、設定ファイルの誤編集や誤削除、復旧手順の誤り、不適切な再起動操作などがサーバーダウンの引き金となります。 ヒューマンエラーは完全に排除することが難しいため、作業手順の標準化や複数人による確認体制の整備など、予防策を講じることが重要です。自然災害や事故による外部要因
地震や台風、洪水、火災などの自然災害や、データセンターでの大規模停電・空調設備の故障などによる事故も、サーバー停止の大きな要因です。これらは発生自体を防ぐことが困難であり、ひとたび起きると広範囲に影響を及ぼします。そのため、災害リスクの少ない立地を選ぶ、無停電電源装置(UPS)を導入する、複数拠点での冗長構成をとるといった備えが求められます。
サーバーリソースの逼迫(CPU・メモリ)
日常的な業務の中でも、CPUの処理能力やメモリの容量、ストレージの空き容量、ネットワーク帯域など、サーバーが持つリソースには限界があります。複数のプロセスが同時に走る、バックアップ処理が集中する、アクセス数が予想を超えるといった要因により、処理能力が限界を迎えると、レスポンスの遅延やサービス停止が発生します。適切なリソース監視と増強計画が不可欠です。
サーバーダウン発生!迅速な原因特定の手順
サーバーダウンが発生した場合、パニックに陥らず、冷静かつ迅速に原因を特定することが、早期復旧と被害拡大防止の鍵となります。以下の手順を参考に、体系的な調査を進めましょう。
手順1:現状把握と影響範囲の確認
まず、何が起きているのかを正確に把握します。「サーバーがダウンした」という情報だけでなく、どのサービスが影響を受けているのか、特定のユーザーだけか全ユーザーか、エラーメッセージは表示されているか、いつから発生しているのか、といった具体的な状況を確認します。関係各所からの情報を集約し、影響範囲を特定することが初動対応の第一歩です。
手順2:各種ログ情報の詳細な分析
サーバーや関連システムは、動作状況に関する様々なログ(記録)を出力しています。システムログ、アプリケーションログ、エラーログ、アクセスログ、セキュリティログなどを時系列で確認し、ダウン直前や発生時刻周辺に異常な記録がないかを調査します。エラーメッセージや警告、通常とは異なるパターンのアクセスなどが原因究明の重要な手がかりとなります。
手順3:リソース使用状況のモニタリング
サーバーのCPU使用率、メモリ使用量、ディスクI/O、ネットワークトラフィックなどのリソース状況を確認します。特定のリソースが異常に高い値を示していないか、あるいは枯渇していないかをチェックします。監視ツールを導入していれば、過去のデータと比較することで、異常な変動を捉えやすくなります。リソース不足が原因である場合、どのプロセスがリソースを消費しているのかを特定する必要があります。
手順4:変更履歴と直近作業の確認
サーバーダウンが発生する直前に、システム設定の変更、ソフトウェアのアップデートやデプロイ、ネットワーク構成の変更など、何らかの作業が行われていなかったかを確認します。変更管理記録や作業報告書などを参照し、関連する作業担当者にもヒアリングを行います。意図しない変更が原因となっているケースは少なくありません。
手順5:外部要因の可能性調査
自社内のシステムに問題が見当たらない場合、利用している外部サービスの障害も疑う必要があります。例えば、契約しているクラウドプロバイダーの障害情報、DNSサーバーの障害情報、連携している外部APIサービスの稼働状況などを確認します。これらの情報は、各サービスの公式サイトやステータスページで提供されていることが多いです。
また、プロバイダ(インターネット接続事業者)側のネットワーク障害や通信経路(BGP)のトラブルなどによって、サーバー自体に問題がなくても「外部から接続できない」状態が発生することがあります。
このようなケースでは、自社の監視システムでは異常が検知されにくいため、プロバイダの障害情報ページやSNSでの報告状況も確認すると良いでしょう。
サーバーダウンから復旧するための応急処置と恒久対策
原因の一次切り分けが終わったら、できるだけ早くサービスを再開し、あわせて再発防止まで視野に入れた恒久対策を進める必要があります。応急処置(短期)と恒久対策(中長期)を、次の 6 ステップで実施しましょう。
1. サーバー再起動とサービス再開(基本的な応急処置)
ソフトウェアの一時的な不具合や、サーバーの処理能力を超える負荷が原因でダウンしている場合、サーバー本体や関連するサービス・プロセスを再起動することで、状況が改善することがあります。これは最も基本的な応急処置のひとつですが、再起動だけでは根本的な原因が解決されていない可能性もあるため、再発の恐れがあります。再起動の前には、トラブルの原因を特定するために必要なログ情報をできるだけ保全しておくことが大切です。
2. 問題箇所の切り離しと縮退運転
システム全体ではなく、特定の機能や一部のサーバーがダウンの原因となっている場合には、問題のある部分を一時的に切り離し、残りの正常な部分だけでサービスを継続する「縮退運転(しゅくたいうんてん)」という対応方法があります。これにより、完全なサービス停止を回避し、最低限の機能だけでもユーザーに提供し続けることができます。
3. バックアップからのデータ復元
ハードウェアの故障やサイバー攻撃、人的ミスなどで重要なデータが失われてしまった場合には、あらかじめ取得していたバックアップデータから復元(リストア)する必要があります。どの時点のデータに戻すか(復旧ポイント)や、どれくらいの時間で復元できるか(復旧時間)を考慮しながら、適切な手順で作業を進めます。
日ごろから、バックアップが確実に取れているか、復元手順に問題がないかを定期的に確認しておくことが大切です。
4. 原因分析と恒久対応の実施
応急処置で一時的に復旧できたとしても、根本的な原因を解決しなければ再発する恐れがあります。ログやシステム構成、直前の操作履歴などをもとに、障害の原因を丁寧に調査し、その内容に応じた恒久的な対応を行うことが重要です。
たとえば、ソフトウェアのバグであればパッチの適用やプログラムの修正、設定ミスであれば見直しと再確認、ハードウェア障害であれば部品の交換など、具体的な対応策を講じましょう。
5. 再発防止のための社内体制と手順の整備
障害が人的ミスや手順漏れによって起きていた場合は、再発を防ぐための体制づくりも必要です。作業手順書やマニュアルの見直し、確認・承認フローの導入、チェックリストの活用、二重確認の仕組みなどを整えることで、ミスの発生を防ぎやすくなります。また、担当者への教育・訓練を定期的に行い、業務の属人化を防ぐことも、安定した運用にとって欠かせません。
6. 代替環境の整備とフェイルオーバーの検討
今後の障害発生時にも迅速に対応できるようにするためには、あらかじめ代替サーバーやクラウド環境を用意し、必要に応じて自動または手動で切り替えられるようにしておく「フェイルオーバー」構成の導入も有効です。重要なサービスを提供している企業であれば、こうした冗長構成を備えることで、万一のトラブルでもサービス継続性を確保できます。
応急対応で被害拡大を防ぎつつ、恒久対策によって同様のトラブルを繰り返さない仕組みを構築することが、安定運用と信頼維持のカギとなります。サーバーダウンを未然に防ぐための効果的な予防策
サーバーダウンは、発生してから対処するよりも、日頃からの予防が最も重要です。以下のような対策を継続的に講じることで、トラブルの発生リスクを大幅に減らすことができます。
1. サーバー監視体制の強化とアラート設定
CPUやメモリの使用率、ディスク容量、ネットワーク状況、サービス応答時間などを常時監視し、異常があれば管理者へ即時通知する仕組みを整備しましょう。これにより、障害の兆候を早期に察知し、深刻なダウンを未然に防ぐことが可能になります。
2. 定期的なメンテナンスとアップデート実施
OSやアプリケーションの脆弱性を突かれないよう、定期的なパッチ適用やバージョンアップを行います。また、不要なファイルの削除やデータベースの最適化といった日常的なメンテナンスも、安定稼働には欠かせません。スケジュールを立てて計画的に実施することが大切です。
3. ハードウェア冗長化と負荷分散の導入
電源ユニットやネットワークカードなどの重要な構成要素を二重化し、機器の一部に不具合があってもシステムが継続稼働できるよう備えます。さらに、ロードバランサーを活用してアクセスを複数台のサーバーに分散することで、特定のサーバーへの負荷集中を回避し、全体の安定性を高められます。
4. データバックアップとリカバリ計画の策定
万が一の障害に備え、定期的なバックアップとともに、復元手順を明文化しておきます。バックアップは別拠点やクラウドなどに保管し、復旧訓練を通じて実効性を確認しておくと安心です。RTO(復旧時間目標)やRPO(復旧時点目標)を明確にし、事業継続に必要な体制を整えましょう。
5. セキュリティ対策の徹底と脆弱性管理
ファイアウォールやWAF、IDS/IPSなどの導入に加え、セキュリティソフトによる端末保護も重要です。また、定期的に脆弱性診断を行い、攻撃リスクのある箇所を早期に修正することで、サーバーダウンにつながるサイバー攻撃を防ぐことができます。
6. キャパシティプランニングとリソース増強
トラフィックやデータ量の増加を見越して、リソースの使用状況を定期的に確認し、必要に応じてサーバーの増設やスペック強化を行います。計画的に容量を見直す「キャパシティプランニング」により、リソース不足によるサーバーダウンのリスクを回避できます。
サーバーダウンの損害に備える「サイバー保険」という選択
サーバーダウンは、アクセス集中、ハードウェア故障、ソフトウェアの不具合、サイバー攻撃、人的ミス、自然災害など、実に多様な原因によって引き起こされます。サーバーダウンが発生すると、金銭的損失や信用の低下など、ビジネスに深刻な影響を及ぼす可能性があります。
万が一サーバーダウンが発生した場合は、冷静に現状を把握し、ログ分析やリソース監視を通じて迅速に原因を特定することが重要です。そして、応急処置と並行して、再発防止のための恒久対策を講じる必要があります。
しかしながら、サーバーダウンによって生じる損害(売上減少・対応費用など)は、対策だけでは完全に防げないこともあります。そこで「万が一」に備える手段として、サイバー保険の活用が注目されています。
事故発生後の損害補償や対応費用に備え、サイバー保険の一括見積で、補償内容を比較・絵検討しておくことをお勧めします。
特に、Webサービス等を提供している企業は、インシデントが起こった際のリスク分散が重要となります。
サイバー保険で補償される主な内容と限界
一般的なサイバー保険では、以下のような費用が補償されます。■事故対応にかかる費用
・事故原因調査・復旧費用
・システムの復旧作業費用
・事故の再発防止策定費用
・弁護士・コンサルティング会社への相談費用
・コールセンターの設置費用
・ユーザーへのお詫び費用
・イメージ回復に伴う広告宣伝費
■損害賠償責任に伴う費用
・損害賠償費用
・訴訟対応費用
■利益損害・営業継続費用
・システム停止中の利益損害や営業継続費用
【補償範囲の意味】
補償範囲はそれぞれ「事故ごとに〇〇円まで支払われる」という設定がされています。
例えば、先に挙げた補償される費用のうち、「事故原因調査・復旧費用」「システムの復旧作業費用」で見てみると、何らかのサイバー攻撃があり自社の業務システムが停止してしまったとした場合、その事故の原因の調査や証拠保全の費用や、システムの復旧までの代替えシステムの費用や新しいサーバが必要となった場合は、その費用も補償されます。
事故発生後の損害賠償や対応費用に備え、サイバー保険の一括見積で、補償内容を比較・検討しておくことをおすすめします。
特にWebサービス等を提供している企業は、インシデントが起こった際のリスク分散が重要となります。
▼サイバー保険はいらない?普及しない理由とは|企業の加入率や被害額も
▼サイバー保険は保険料は月額いくら?料金相場から補償内容、選び方まで徹底解説!
▶ サイバー保険 一括見積はこちら(無料)
当サイトを運営する「ファーストプレイス」では、
大手5社のサイバー保険の保険料を、無料で一括比較・見積りいただけます。
- 東京海上日動火災保険株式会社
- 三井住友海上火災保険株式会社
- 損害保険ジャパン株式会社
- あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
- AIG損害保険株式会社
ECサイトやWebサービスを提供している企業様は、IT業務を提供する企業様向けの「IT業務用サイバー保険一括見積サイト」もご検討ください。
よくある質問(FAQ)
Q1. サーバーダウンとは、具体的に何が起きている状態ですか?
サーバーダウンとは、社内外のシステムやWebサービスが一時的または継続的に利用できない状態のことです。完全に停止するだけでなく、「つながったり切れたりする」「動作が極端に遅くなる」といった症状も広義のサーバーダウンに含まれます。
Q2. 404や503などのエラーは、サーバーダウンとどう関係していますか?
404エラーは「指定したページが存在しない」というもので、URLのミスやページ削除が原因です。サーバー自体は正常に動作しており、サーバーダウンとは直接関係ありません。
一方、503エラーは「一時的にサービスが利用不可」という意味で、サーバーダウンや過負荷、メンテナンス中などが原因となるため、サーバーダウンの一種とされます。
Q3. 自社サイトが落ちているか、どうやって確認すればいいですか?
社内の問題か外部要因かを切り分けるのが重要です。
・複数の回線や端末からアクセスしてみる
・外部の監視サービス(DownDetectorなど)で確認する
・クラウドやホスティング事業者の障害情報を確認する
・自社のサーバー監視ツールで状況をチェックする
Q4. サーバーダウン時、まず何をすべきですか?
障害範囲の把握と初動対応が重要です。
1. 影響範囲(Webサイト、メール、社内システムなど)を整理
2. 社内要因か外部要因かを切り分け
3. ホスティング会社やクラウドベンダーの情報を確認
4. 関係者に状況と見通しを共有する
Q5. サーバーダウンを防ぐには、どんな対策が有効ですか?
・アクセス集中への対策(CDN導入、スケーリング設定)
・サーバー監視とアラート通知の整備
・バックアップと冗長構成の導入
・WAFやIPSなどセキュリティ対策の実装
・障害時の対応手順や連絡フローの整備